公務員のデザイン・クリエイティブ枠を目指しているあなたへ。
勉強も、政策理解も、作品づくりも──やることは山ほどあるけれど、「今日は何もできない…」という日、ありませんか?
そんな日は、ただ焦って時間を過ごすよりも、自分の感性をそっと育てておくことが、長い目で見ればとても大きな意味を持ちます。
この記事では、やる気が出ない日にも実践できる、“小さくて前向きな行動”を5つご紹介します。
デザイン的視点や発想をゆるやかに保ちつつ、無理なく進めるヒントになれば幸いです。
街の掲示物をじっくり観察してみる

日常の中には、行政や地域団体が発信する情報であふれています。
役所の掲示板、商店街の案内、公共施設のポスター……これらはすべて、“住民に伝える”ためのアウトプット。
つまり、公務員のクリエイティブ職が将来関わる現場そのものです。
公共物に触れる日常を「教材」に変える
「このチラシ、見やすいな」「読みにくいけど、なぜそう感じるんだろう?」といった疑問が浮かんだとき、それはすでに“分析する目”が育ち始めている証拠です。
どんな色を使っているか、文字の配置はどうなっているか、写真は何を意図して選ばれているのか──。
たとえば、赤が多すぎると注意喚起になりすぎたり、フォントが細すぎると高齢者には読みにくかったりします。
こうした細部への気づきは、机の上では得にくい、リアルな視点です。
公共の場にある掲示物はすべてが教材。散歩がてら街を歩くだけでも、自分の観察力や批判的思考が鍛えられていきます。

気づきをストックするだけでも前進になる
観察したものの中で「これは良い」と思ったデザインや、「改善できそう」と感じた点は、すぐに忘れてしまいがちです。
そんなときは、スマホで写真を撮って“掲示物コレクション”を作ってみてください。
そして、空いた時間にその写真を見返しながら「自分ならこう直すかも」と仮想のリデザインをしてみる。
そうすることで、アウトプットの力が鍛えられます。さらに、将来のポートフォリオで「掲示物の改善提案」として活用することも可能になります。
自治体の広報誌を検索して読み比べてみる

ちょっと気分転換したいときは、「◯◯市 広報誌」と検索してみましょう。
多くの自治体がPDFで広報誌を公開しており、行政の広報デザインの実例集として活用できます。
広報誌は行政×デザインの完成形
広報誌は、ただ情報を載せるだけではなく、どの情報をどのように構成すれば住民に届くかを緻密に考えて作られています。
トピックの配置順、見出しのつけ方、図版の使い方ひとつひとつに意図があり、それは“行政のデザイン思考”の現れです。
たとえば、特集記事では市民インタビューを取り入れることで共感を生んだり、数字を図解化することで理解のハードルを下げたりする工夫がされています。
そうした細かな演出を読み取ることで、自分の中に「伝える構成とは何か」という感覚が蓄積されていきます。
気に入った事例は保存・分析しておこう
「このデザイン、わかりやすい」「この配色は落ち着く」など、気に入ったレイアウトや構成があれば、それをスクリーンショットで保存して“良い事例フォルダ”を作ってみましょう。
それらを比較することで、自分の好みや評価基準が明確になっていきます。
また、面接やプレゼンの際に「〇〇市の広報誌では、こうした構成が効果的だったと分析しました」といった根拠づけの材料にもなります。
単なる読み物を、自分の武器に変えるチャンスです。
図書館や市民センターで地域のチラシを観察してみる

近所の図書館や公民館に立ち寄ってみると、掲示板やラックにはたくさんの地域チラシが置かれています。
これは、行政職員だけでなく、町内会、地域団体、子育てサークルなど、**“一般市民による情報発信”**の現場でもあります。
不完全なデザインだからこそ、学べる視点がある
地域のチラシは、プロのデザイナーが作るものではないことが多いため、フォントが多用されていたり、行間が詰まりすぎていたりすることもあります。
逆に、手書きの温かみがあることで親しみが持てたり、文字サイズにメリハリがなくて読み飛ばされたりすることも。
こうした「うまくいっていない点」を観察し、改善の余地を考えることが、実際の業務でも非常に重要になります。
つまり、批判ではなく、“もっと良くするには?”という視点を育てる練習です。
“住民視点”を持つ訓練として最適
行政の仕事では、“伝えたいこと”より“伝わること”が優先されます。どれだけ正しい情報でも、伝わらなければ意味がありません。
その視点を持つには、一般市民が何に戸惑うか、何で情報を受け取れないのかを知る必要があります。
地域のチラシを分析することで、そうした“つまずき”を実感することができます。
「住民の立場だったら?」と自問するだけで、伝えるスキルが育っていきます。
店舗レイアウトを観察して“動線設計”を感じ取る
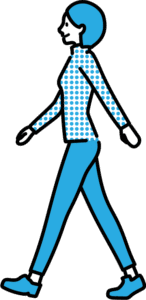
ショッピングモールや大型店舗に行く機会があれば、“買い物”の視点から離れてみましょう。
無印良品やユニクロなど、レイアウトや視線誘導が考え尽くされた空間を歩くだけでも学びになります。
文字、配置、動き──空間そのものが教材になる
店舗の設計には、「人をどのように動かすか」という工夫が詰まっています。
POPの配置、通路の幅、棚の高さ──それらはすべて“行動デザイン”です。
たとえば、案内表示が自然と目に入る場所にあれば混雑を避けられるし、配置が直感的であれば商品選びのストレスも減ります。
行政施設でもこれは同じ。わかりにくい窓口案内や、読みにくいポスターは市民のストレスになります。
空間から学ぶ力は、現場対応力にもつながる
「何となく分かりにくい」と感じたときに、「なぜそう思うのか?」を考えるクセをつけましょう。
それは、行政職において現場で必要となる“感覚的な改善提案力”を養う練習です。
現地調査や利用者対応の中でも、空間への気配りは必須。
日頃から他者の目線で空間を観察することで、現場に強いクリエイティブ職になれます。
フリーフォントをひとつDLしてみる

「今日は本当に何もしたくない……」
そんな日は、自分を責める代わりに、**“1フォントだけ探してみる”**という気軽なタスクをやってみませんか?
フォント選びは、実は行政デザインの基礎
フォントにはそれぞれ“伝える雰囲気”があります。たとえば、明朝体は公的な印象を与え、ゴシック体は視認性が高く、丸ゴシックは親しみを演出します。
行政の広報物では、これらのフォントを状況に応じて適切に使い分けることが求められます。
フォント探しは単なる趣味ではなく、「どう伝えたいか」「誰に伝えたいか」を考える訓練そのものです。
自分の中の“伝えるトーン”を増やすことで、表現力が磨かれていきます。
「今日はこれだけ」でも積み重ねになる
気に入ったフォントをひとつ保存し、名前をメモしておくだけでも十分な収穫です。
その日の気分に合ったフォントを選ぶだけでも、“デザインとの接点を保つ”ことができます。
いずれポートフォリオをつくる際や、政策広報資料の改善案を出す際に、「そういえばこの書体が合いそう」と思い出せたら、そのフォント収集は確実に役立ちます。
小さな行動も、長い目で見れば立派な投資です。

自分を責めない“感性メンテナンス日”という選択肢

「やる気が出ない」「今日も手が動かなかった」──そんな日に必要なのは、反省ではなく、“ゆるやかな前進”です。
試験勉強や制作に向かうことが難しい日でも、街を見て、文字を見て、誰かの伝えたい気持ちに触れてみましょう。
公務員のクリエイティブ職に必要な視点や感性は確実に育っています。
- どうすれば伝わるか
- どこでつまずいてしまうのか
- 誰に届けるかを考える目を持つこと
これは、日常の中でしか磨かれない力です。そしてその力こそが、行政現場で最も必要とされる“市民に寄り添う表現力”です。
何もしなかった日、ではありません。ちゃんと“考えて、感じた日”として、自分を褒めてあげましょう。
また元気が出てきたら、きっと自然と動き出せます。焦らず、自分のペースで。
今日のあなたも、確実に前に進んでいます。









コメント