昨今、公務員の世界でもデザインの力を活用して、行政サービスに貢献しようという動きが活発になってきています。
ホームページや採用活動のためのパンフレット、チラシや施策に至るまで、とてもキレイにデザインされたものが多くなってきました。
かつてデザインに関わる仕事と言えば、美大生やデザイン専門学校生の専売特許でした。
ですが、今や公務員の世界でもデザインの重要性が注目されてきています。
令和の時代に入ってようやくデザインの社会的地位が上がってきた、と言えるのではないでしょうか。
そこで今回は、安定した身分を保障しながらデザインの仕事ができる「自治体のデザイン・クリエイティブ枠」について解説します。
この記事を読めば、公務員という身分を保証しながら、デザインの仕事やデザイナーに近い仕事に就けるかも知れません。

美大に行くのは諦めていたけど・・・
という人にとっても、公務員になってデザインの仕事ができるならやってみたい!という人もいるのではないでしょうか。
デザインの仕事が好きでクリエイティブ関連のお仕事に関わっていたいという人は、ぜひ今回のブログ記事を読んで自分の将来の選択肢を広げてみてください。
美大に行きたかった人へオススメの、デザイン・クリエイティブ枠採用とは?

そもそも公務員試験で「デザイン・クリエイティブ枠」を設置したのは、2019年度の採用試験からで神戸市が政令指定都市が初めての試み。
枠組みとしては、デザイナー職ではなく既存の事務行政職と同じカテゴリーとなります。
ただ、専門性に特化しているという点で一般の事務職とは異なり、筆記試験の負担が軽減されている自治体も多いです。
今までに、学校や社会人スクール等で美術、デザイン、建築、音楽、映像などを学んできた人でも、公務員試験自体は視野に入れていなかった人が多いでしょう。
かくいう自分も、過去にデザイン業界を目指していた時は公務員試験を受けようとも思いませんでしたし、その時代にはクリエイティブ枠というものすらありませんでした。
自治体の意図としては、今まで行政になかった発想や価値観、多様な才能を持った人材が集まることで、今までにない化学反応が起こることを期待しているのでしょう。

美大生からもジワリと人気。デザイン・クリエイティブ枠採用増加の理由

かつて、公務員の仕事と言えば、同じような仕事を毎日淡々とこなし、マニュアルに沿って正確に仕事をこなす人が優秀な人材でした。
ですが、令和の時代は多様な価値観・ライフスタイルの変化に伴い、昭和や平成の時代のような画一的なサービスを提供するだけでは限界が来ています。
そのため、デザイン思考やクリエイティブな発想ができる人、デザインコンサルティングのような形で社会課題を解決に導く人材が、より強く求められています。
公務員のクリエイティブ枠採用が増えてきている理由は、このような時代背景も影響していると言えるでしょう。
美大へ行きたかった人へおすすめの就職・転職候補先の主な自治体
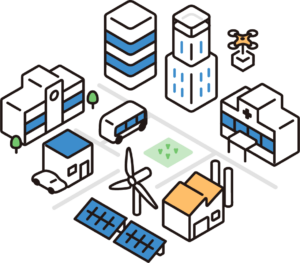
ここでは、現在までに「クリエイティブ枠」採用をおこなった自治体についてご紹介します。
もし、自分の住んでいる地域の近く、ゆかりのある場所であれば、志望動機もつくりやすいでしょう。
- 兵庫県神戸市
- 千葉県市川市
- 富山県高岡市
- 新潟県長岡市
- 【番外編】デジタル庁
それぞれの自治体ごとに特徴があるので、1つずつ順番に見ていきましょう。
兵庫県神戸市
先ほども少し触れましたが、公務員の「デザイン・クリエイティブ枠」を設置した自治体としては、政令指定都市では兵庫県神戸市が初めてということになります。
求められる人材としては以下のように記されています。
- デザイン・美術・音楽・映像などの素養があり、培った思考などを活かして、創造的に仕事を企画・実現できる人
- 自身の専門分野の知識・経験が豊富な人に限らず、不得意分野を含め様々な分野に関心がある人、好奇心が旺盛な人
引用:神戸市:2024年度 デザイン・クリエイティブ枠(大学卒、高専・短大卒) (kobe.lg.jp)
ちなみに、2023年度は3名の職員募集があり、結果は以下の通り。
| 受験者数 | 申込者数 | 受験者数 | 最終合格者数 | 競争率 |
| 大卒 | 46 | 43 | 3 | 14.3 |
| 高専・短大卒 | 5 | 3 | 0 | – |
| 合計 | 51 | 46 | 3 | 15.3 |
引用:神戸市:2023(令和5)年度職員(デザイン・クリエイティブ枠)採用試験の合格者決定 (kobe.lg.jp)
倍率は約14~15倍なので簡単に受かる試験ではありませんが、もし興味があるなら受験してみる価値はあると思います。
ただし、受験資格に年齢制限があるので、その点は注意しておきましょう。

千葉県市川市
千葉県市川市でも2019年度より、行政職の採用に「クリエイティブ枠」を設置しており。求める人材は以下のようになっています。
- 芸術分野に素養があり、創造し表現することが得意な人
- これまでの行政にない斬新な視点や発想力、企画力のある人
引用:令和3年度 市川市職員採用試験受験案内〔 職種:一般行政職 事務(クリエイティブ枠)〕
さらに、市川市では2003年度より「年齢・学歴制限撤廃枠」も設けているため、より多くの人に門戸が開かれています。
ただし、過去の採用情報を見ると、2022年度、2023年度はクリエイティブ枠の採用自体が見送られているようです。
ちなみに2019年度、2020年度、2021年度は募集があったようで、2021年度の結果は以下の通り。
| 職種 | 募集 | 応募 | 受験 | 一次合格 | 最終合格 | |
| 行政職撤廃枠 | 事務(クリエイティブ枠) | 数名 | 41 | 38 | 5 | 2 |
両年度ともに、採用は数人なのでこちらも倍率だけみると激戦となってますね。
多くの人に門戸が開放されている一方、毎年度募集があるわけではなさそうなので、こまめに採用情報をチェックしておくと良いでしょう。
富山県高岡市
富山県高岡市でも、2023年度より「デザイン・クリエイティブ枠」が新設されました。
富山県といえば、3年に一度おこなわれている「世界ポスタートリエンナーレトヤマ」が有名で、コンテストのレベルは非常に高く、クリエーターやデザイナーの登竜門にもなっています。
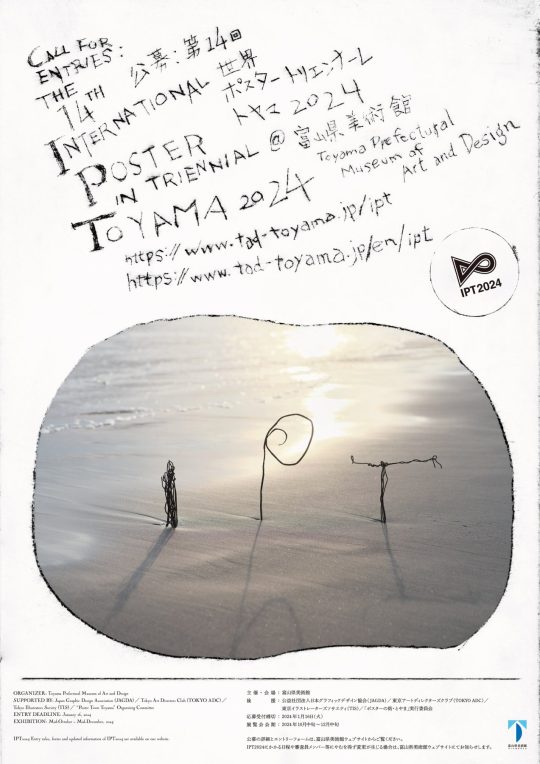
受験資格などを確認して、次回の試験を興味があれば受験してみるのも良いでしょう。
募集要項には、求められる人材自体ははっきりとは明記されていませんが、それに近い職務内容についの記載はありましたが、現在はリンク切れとなっています。
- デザイン・クリエイティブ分野に関わる企画・ 立案などを通じて産業支援業務等に従事するほ か、産業振興等の関連事務を含む行政事務全般 に従事する。
(掲載終了):高岡市職員採用試験(令和6年4月採用)令和5年度募集要項〔事務職(デザイン・クリエイティブ業務)-大卒・社会人経験者〕
今年度新設されたばかりの枠なので、どれくらいの倍率になるかはわかりませんが、スタートラインはみんな一緒ですので、ある意味狙い目の採用試験かもしれません。
受験資格に年齢制限があるため、この点には注意しておきましょう。

新潟県長岡市
新潟県長岡市でも、2023年度より「デザイン・クリエイティブ枠」が新設されました。
求める人材と職務内容は以下のようになっています。
- デザイン力や創造力、発想力をもって、施策の立案・発想ができる人を募集
- なお、「一般事務職員(デザイン・クリエイティブ人材)」の最初の配属先は、政策・ 企画、広報、観光振興、文化振興、まちづくり関連などの部署を想定しています。
引用:令和5年度(前期日程)長岡市職員採用試験案内
ちなみに、2023年度は5名の職員募集があり、結果は以下の通り。
| 職種 | 申込者数(人) | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 倍率(倍) |
| 一般事務Ⅰ種 (デザイン・クリエイティブ人材) | 45 | 39 | 5 | 7.8 |
引用:採用試験実施状況 (city.nagaoka.niigata.jp)
募集人数自体が5人と、他の自治体に比べて採用人数も多めのため、倍率自体は7.8倍に収まっています。
こちらも、受験資格に年齢制限が設けられているため、その点には注意です。また、いずれにしもて狭き門であるということに変わりはありません。

【番外編】デジタル庁
番外編として、デジタル庁の「デザイン・クリエイティブ枠」についてもご紹介します。
現在、デジタル庁では「デザイン・クリエイティブ枠」という名称ではなく、職種ごとに
- 「ビジュアルデザイナー」
- 「プロダクトデザイナー」
- 「デザインプログラムマネージャー」
- 「デザインコミュニティマネージャー」
という職種で、完全なる専門職を求めているようです。
身分としてはデジタル庁の職員ではあるものの、非常勤の一般職国家公務員となり、年度更新でおおむね1−5年ごとの任期があります。
先にご紹介した自治体の「デザイン・クリエイティブ枠」と異なり、正規職員ではなく、非常勤職員という任用形態となっているのが特徴。
また、完全に専門職としてビジュアルデザイナー等を募集しているため、ここでは【番外編】としてご紹介することにしました。
ちなみに求める人物像を見てみると、以下のようになっています。
- デジタル庁が掲げるミッション、ビジョン、バリューへの強い共感
- 社会全体のデジタル化に向けて、業務を人任せにせず、当事者意識をもって課題を解決していくマインド
- 「全体の奉仕者」たる国家公務員に求められる高い倫理観
引用:【E_02】ビジュアルデザイナー – デジタル庁 (herp.careers)
これらの理念に共感できれば、将来の選択肢の1つに加えても良いでしょう。
年齢制限については記載が無いので、特に制限は無いと思いますが、気になる方は問い合わせフォームから質問してみても良いでしょう。
美大へ行きたかった人の就職先への門戸は、徐々に広がってきています!

今までの公務員試験では、筆記試験重視の画一的な試験が一般的でした。
昨今では、少しずつ面接試験にも比重が置かれるようになってはいますが、デザイン・クリエイティブ枠のような募集がおこなれるというのはかなり革新的です。
今まではデザイナーの仕事に興味はったけど、本業にするには躊躇していた人も、公務員という身分でデザインの仕事ができるならやってみたいという人も増えていくでしょう。
まだ、数えるほどの自治体でしか「デザイン・クリエイティブ枠」の募集はありませんが、これらの自治体で採用された人が業務で結果を出せば、今後のこの動きは全国的に広がっていくはずです。
一方で、公務員試験の学校や予備校でも、はじまったばかりの「デザイン・クリエイティブ枠」に特化した対策をするというのはまだまだ難しい状況です。
志望する人は、ぜひこのブログを読んで対策を練ってみてください。
新しい職種ということで、デザインのお仕事に近い働き方のできる自治体の「デザイン・クリエイティブ枠」の対策を兼ねた記事も、徐々に増やしていけたらと思っています。









コメント