「公務員に、デザイン?」
かつて民間でグラフィックデザイナーとして働いていた私にとって、この組み合わせは意外で、とても興味を惹かれるものでした。
現在は事務系の仕事をしていますが、生活の中でふと目にする自治体の広報物やお知らせに、「この情報、もっと伝わる形にできるのでは?」と感じることが少なくありません。
そんな中で知ったのが、「公務員のデザイン職」という存在です。
このテーマについて調べていくうちに、行政の中で“デザイン”が果たす役割や必要性が、民間とはまた異なる切実さを持って求められていることが見えてきました。
本記事では、元・グラフィックデザイナーであり現在は事務系職員として働く私の視点から考察をおこないます。
なぜ行政がデザインを必要としているのか、その背景や求められるスキル、そして今後の可能性について掘り下げていきます。
公務員が“デザイン”を求めるようになった理由

行政がデザインを重視し始めたのは、単なる見た目の改善ではなく、情報を正しく、わかりやすく、確実に「伝える」ことの重要性が増しているからです。
特に、以下の3つの背景が大きな理由です。
- 住民視点での「わかりやすさ」が求められている
- UX(使いやすさ)という視点が行政にも必要になってきた
- 「伝える」から「伝わる」広報へ
これらを通じて、“情報を届ける力”としてのデザインが、行政の現場でも欠かせない存在となりつつあります。
また、最近ではデザイン専門職の採用に加え、事務系職員が広報・地域連携・市民参加といった部署で、ビジュアルの工夫や資料設計などに関わるケースも増えてきました。
住民視点での「わかりやすさ」が求められている
高齢者や外国人、子育て中の方など、多様な背景を持つ住民に向けて、わかりやすい言葉や構成、図解などを使った情報発信が求められています。
たとえば札幌市が取り組んでいる「やさしい日本語」の広報物や、誰でも理解できる図解つきのチラシなどは、まさにデザインの力で“伝わる”を実現している例です。
UX(使いやすさ)という視点が行政にも必要になってきた
行政サービス手続きや申請書類が「わかりにくい」「使いにくい」と言われることは少なくありません。
最近ではデジタル庁を中心に、行政サービス全体のUX改善が進められています。
- フォームの構造を見直す
- 専門用語を避ける
- アイコンや図でナビゲーションをサポートする
これらの工夫は、デザインの視点からこそ可能な改善です。
「伝える」から「伝わる」広報へ
ポスターやチラシを配るだけでは、行動は起きません。住民が「行動できる情報」へと変えるためには、見せ方や配置、トーンなどの設計が重要です。
たとえば防災ポスターなら、
- どこに貼れば効果的か?
- どんな文言が緊張感を伝えるか?
- 高齢者が見やすい配色か?
といった観点から、丁寧に設計される必要があります。

公務員の現場で求められる“デザイン”とは?
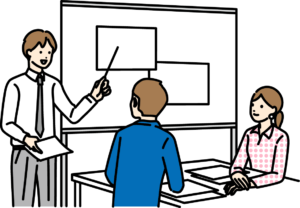
では、公務員のデザイン職やデザインに関わる業務では、どんな力が求められているのでしょうか。
特に以下の2点が重要視されています。
- 見た目ではなく「構造」を設計する力
- 協働型プロジェクトでの“つなぎ手”としての役割
これらのスキルは、グラフィックやWEBに限定されず、事務系の職員でも活かせるものです。
見た目ではなく「構造」を設計する力
読み手が迷わず情報を受け取れるように、情報を整理し、順序立ててレイアウトを設計する能力です。
- 優先順位の明確化
- 見出しと本文の流れの整理
- 補足情報の視覚的整理
これらは、デザイン経験者だけでなく、書類作成や資料づくりに携わってきた人にも応用できるスキルです。
協働型プロジェクトでの“つなぎ手”としての役割
自治体の多くの業務は、住民や関係者との協働で進められています。
- ワークショップの設計
- ヒアリングや意見収集
- 複数部署との調整
これらのプロセスで、見える形に落とし込みながら合意形成を進める「可視化スキル」も、行政で求められる重要なデザイン力です。
公務員デザイン職を目指す価値とは?

行政におけるデザインの可能性は、今まさに広がっている最中です。ここでは、その中でも特に注目すべき価値を2つ紹介します。
- 「社会をよくする」デザインに関われる
- まだ確立されていない分野だからこその可能性
「社会をよくする」デザインに関われる
行政デザインは、日常生活の改善や誰かの不安の解消に直接つながる仕事です。
- 子育て支援の説明資料
- 高齢者向けの手続き案内
- 外国人住民向けの翻訳チラシ
事務系職員でも、広報や政策立案の現場でこれらに携わるチャンスがあります。
「誰かのためになるデザイン」に興味があるなら、十分に挑戦する価値があるフィールドです。
まだ確立されていない分野だからこその可能性
行政内でのデザイン職は、まだ制度や理解が十分に整っていない分野です。
- 新しい視点をもたらす人材になれる
- “考えるデザイン”を持ち込める先駆者になれる
- 自分のスキルで行政文化を変えていける
整備されていないからこそ、関われるチャンスがあり、活かせる余地も大きいのです。
どんなスキルがあると役立つ?

公務員のデザイン職や、それに関わる業務で活きるスキルにはさまざまなものがあります。
- Illustrator / Photoshop の基本操作
- Canva や PowerPoint を使った図解作成
- UX / サービスデザインの基本理解
- 情報設計(インフォメーション・アーキテクチャ)
- ファシリテーションとヒアリング力
これらのスキルは、専門的な知識だけでなく、「伝える力」全般に役立ちます。
まずは学び始めるところから

本格的にキャリアチェンジを目指す前に、「試しに触れてみる」ことはとても大切です。
特に公務員を目指している方や、すでに事務系職員として働いている方でも、デザインの考え方やツールの基本を知るだけで、業務の幅が大きく広がります。
デザインと聞くと「センスが必要」「美術の才能がいる」と思われがちですが、行政におけるデザインは、むしろ論理的な設計力や整理力の方が重要です。
だからこそ、実務経験がなくても、学び方次第で大きく近づくことができます。
スキル習得の第一歩として、多くの人が取り組んでいるのがオンライン講座です。実務をしながらでも無理なく学べ、応用しやすい内容が揃っています。
デイトラ
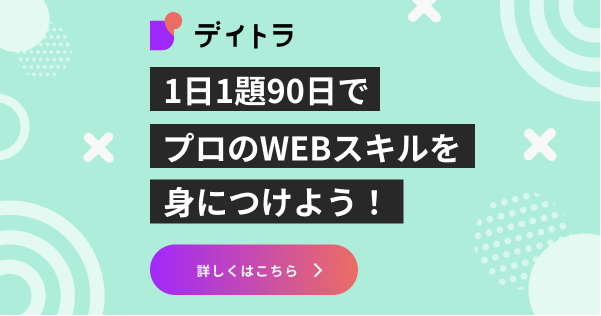
短期間でUI/UXやWebデザインが学べる。実践的な課題も充実しており、実務に直結するスキルを効率よく習得できます。
✅【デイトラ公式サイトはこちら】→業界最安級、実績・口コミ多数!仕事に繋がるWebスキルを身につけるなら ![]()
デジハリ

デザインとビジネスの両面から学べる。UI/UXやWebデザインに加え、ポートフォリオ支援もあり、転職や副業にも活かしやすい内容です。
✅【デジハリ公式サイトはこちら】→デジハリ・オンラインスクール|Web、CG、映像、プログラミングの通信講座の申込
「仕事の合間に触れてみる」「週末に動画を見る」——そんな小さな習慣からでも、自分の視野や選択肢は広がっていきます。
スキルを得ることは、選択肢を増やすこと。
まずは「少し学んでみる」だけでも、見える景色は変わってきます。 まずは「少し学んでみる」だけでも、見える景色は変わってきます。
公務員のデザイン職に向けた最初の一歩

民間で培ったデザインスキルや「伝える力」は、行政の現場でも大いに活かせる時代になってきました。
たとえデザイン専門職での採用でなくても、広報や地域連携、住民対応の部署など、さまざまな現場でデザイン思考は求められています。
「伝える」ことに関心がある、誰かの生活を少しでもよくしたい、そのために自分のスキルを役立てたい。 そう思える人なら、きっと行政の現場でも力を発揮できるはずです。
今はまだ、整備されていない制度や仕組みも多いかもしれません。
けれど、だからこそ挑戦する価値があり、自分の存在意義を実感できる場所でもあります。





コメント