「デザインを仕事にしたい。でも、民間ではなく“公務員”という選択肢も気になる──。」
そんなふうに悩んでいるあなたは、もしかすると公務員のデザイン職=事務職という肩書きに少し違和感を覚えているかもしれません。
実際、「クリエイターなのに事務職って、どういうこと?」という声は少なくありません。
本記事では、民間のデザイナーとの違い、行政の現場で求められるスキル、そして事務職という枠組みの中にある“リアルなクリエイティブのかたち”を掘り下げていきます。
志望動機に迷っている人や、「この進路で本当にいいのか?」と立ち止まっている人にこそ、読んでいただきたい内容です。
「デザイン職なのに、事務職?」という疑問の正体

この章では、その違和感の正体と、公務員のデザイン職の立ち位置について整理していきます。
「デザイン職」と「事務職」という、一見矛盾するような言葉が並ぶ理由には、行政の仕組みと職務の幅広さが関係しています。
ここでは、デザイナー志望の方が感じるであろう素朴な疑問を一つずつ紐解いていきましょう。
- “事務職”と聞いて、なぜ違和感を覚えるのか
- 民間デザイナーと何が違う?公務員のデザイン職の役割構造
- “制作”より“調整”がメイン?行政の現場で求められる力とは
これらの視点を通じて、公務員のデザイン職が持つ独自の立ち位置や役割について、詳しく解説していきます。
“事務職”と聞いて、なぜ違和感を覚えるのか
多くの人が「デザイン=制作職」という認識を持っており、手を動かしてものを作ることが仕事だと考えています。
民間企業や制作会社での職種名も「デザイナー」「ディレクター」といった明確なものが多く、公務員の募集要項で「事務職(デザイン担当)」と記されていると、違和感を覚えるのは当然です。
これは、公務員の職種区分と、仕事の実態との間にギャップがあるためです。
民間デザイナーと何が違う?公務員のデザイン職の役割構造
民間のデザイナーは、商品やサービスの価値を視覚的に表現し、消費者に訴求するのが主な役割です。
一方で、公務員のデザイン職は「伝える」よりも「わかりやすく届ける」「誤解を防ぐ」といった公共性を意識した表現が求められます。
また、制作だけでなく、行政内の関係部署と協力しながら企画を立て、調整し、時に外部と連携する役割も担います。
制作以上に「場を整える力」が問われるのです。
“制作”より“調整”がメイン?行政の現場で求められる力とは
行政の現場では、チームプレーと調整能力が非常に重要です。ポスターひとつ作るにも、広報課、担当課、法務課などとのやりとりが必要になります。
また、住民への説明責任や公平性の観点から、表現内容に制約が多いのも事実です。
こうした中で、単に「いいデザイン」をするのではなく、「関係者全員が納得する表現にまとめあげる」という調整力が、デザイナーにも求められます。
公務員のデザイン職で、実際にできること・できないこと
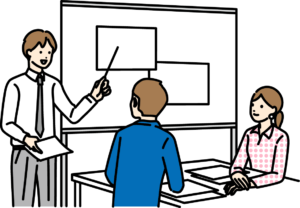
民間と比べて「自由が利かなそう」「デザインっぽくない」と思われがちな公務員の現場。
しかし、実際には“できること”も“できないこと”も存在します。ここでは、そのリアルな違いを明らかにします。
日々の業務で関わる具体的なタスクを見ていくと、一般的なデザイン職との違いが明確になってきます。以下のような点が代表的です。
- 外注とのやりとり、内部調整、企画立案…裏方の多さはむしろ強み
- Photoshopが得意?だけじゃ評価されない世界
- 住民目線・行政手続き・公共性——「届け方」に全力を注ぐ
それぞれの仕事内容には共通点もありますが、求められる姿勢や視点は少しずつ異なります。
ここからは、公務員のデザイン職が日々の業務でどのように動いているのか、具体的に見ていきましょう。
外注とのやりとり、内部調整、企画立案…裏方の多さはむしろ強み
実際の制作物は、外注のデザイン会社や印刷会社に依頼することが多いです。
公務員のデザイン職は、何を作るか、どのような意図で伝えるか、その全体像を描くプロデューサーのような立場になります。
複数の部署と調整を重ね、住民のニーズと行政の目的をつなぐ役割が求められます。
Photoshopが得意?だけじゃ評価されない世界
「デザインソフトが使える」だけでは通用しません。
むしろ、限られた時間や予算、法的制約のなかで「伝えたいことを整理し、誰にでも伝わる形に変換する力」が評価されます。
ソフトはあくまで手段であり、何をどう伝えるかという思考力と構成力が重視されるのが行政デザインの特徴です。
住民目線・行政手続き・公共性——「届け方」に全力を注ぐ
行政が対象とするのは、多様な年齢層・言語・価値観をもったすべての住民です。そのため、視認性・読みやすさ・誤解のない表現が最優先されます。
デザイン性よりも、情報の確実な伝達が求められる場面が多く、その分「届け方」の設計には非常に神経を使います。
伝わるまでがデザイン──そんな姿勢が行政の現場では根付いています。

それでも、あえて「事務職として」クリエイティブを選ぶ理由

それでもなお、民間ではなく行政を選ぶ人がいます。この章では、「なぜあえて事務職なのか?」に対する答えを掘り下げます。
一見地味で制約の多そうな行政の世界で、なぜあえてクリエイターとしての道を選ぶのか。そこには、民間にはないやりがいや、社会に届く実感を得られる魅力があります。
- “直接手を動かす”以外のデザインがある
- 派手さより、確実に社会に届く実感
- 制度やルールの中で工夫するからこそ、スキルが鍛えられる
これらの観点から、公務員という選択をあえて選ぶクリエイターが増えています。
民間とは異なるアプローチで社会に関われる実感や、長期的に影響を与えられる達成感が、その動機のひとつになっているのです。
“直接手を動かす”以外のデザインがある
デザインとは単なるビジュアル制作だけではありません。制度設計、仕組みづくり、合意形成といった“目に見えない構造”を整えることも、立派なデザインの一部です。
公務員のデザイン職は、まさにその“見えないデザイン”を日常的に行う立場にあります。
派手さより、確実に社会に届く実感
民間の仕事では「かっこいい」「話題になる」デザインが評価されることも多いですが、公務員のデザイン職では「暮らしが少し便利になった」「申請がスムーズにできた」といった、生活者の行動変容こそが成果です。
SNSの反応よりも、目の前の人の納得と安心が重要視されます。
制度やルールの中で工夫するからこそ、スキルが鍛えられる
制限があるからこそ、創意工夫が生まれます。たとえば使用できる色数や文字サイズが制限されている中で、いかに見やすく、いかに魅力的に伝えるか。
限られた条件のなかで効果的に伝える経験は、他のどの現場でも活かせる普遍的なスキルです。
事務職だからこそ広がる、キャリアの選択肢
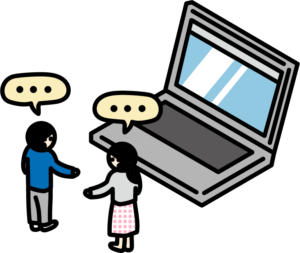
公務員のデザイン職は、事務職という枠組みの中で働くからこそ、キャリアの幅が広がる一面もあります。
行政職員としての基盤を持ちながら、デザインの専門性を武器にすることができる。このユニークな立ち位置は、将来的な働き方の選択肢にも大きな影響を与えます。
以下では、その理由を詳しく見ていきます。
- デザイン以外のスキルが伸びる(予算・広報戦略・調整力など)
- 「現場を知るクリエイター」としての強み
- 将来、どんな働き方にも転用できる“公共デザインの眼”
単なる制作力にとどまらず、マネジメントや政策設計まで視野に入れたスキルが育つのが、公務員のデザイン職の特長です。
以下のような点から、将来の働き方が大きく広がる可能性があります。
デザイン以外のスキルが伸びる(予算・広報戦略・調整力など)
公務員のデザイン職では、広報業務のほかにも、予算の確保、スケジュール管理、庁内外との調整など、多様なスキルが求められます。
これらの経験は、将来的にディレクター職やマネージャー職に就く際の大きな武器になります。
「現場を知るクリエイター」としての強み
市民の声を直に聞き、現場の課題を肌で感じられる立場にいることで、より実効性のある提案ができるようになります。
机上の空論ではなく、リアルな課題に即した表現ができる力は、どの業界でも重宝されます。
将来、どんな働き方にも転用できる“公共デザインの眼”
誰に何をどう届けるかという「公共性」の視点は、行政を離れても活用できます。
NPO、教育、地域振興、国際協力など、より広いフィールドでその視点が求められる時代です。
「事務職」にこだわらず、“本質”に目を向けてみよう

ここまで読み進めていただいたあなたなら、公務員のデザイン職が「事務職」の一言で片付けられない、奥深い職種であることがわかったはずです。
公務員のデザイン職は、見た目の派手さやスピード感のある成果が求められる民間の仕事とは異なり、「誰かの生活に寄り添い、社会の基盤を支える」ことが主眼にあります。
そのため、地味であっても、確実に必要とされる仕事が数多く存在します。
制度や仕組み、伝達手段といった見えにくい部分を整えることで、人々の行動が変わり、生活がよりスムーズになる。
そんな実感を持ちながら働ける環境は、クリエイターにとって新たな視点を得られる貴重なフィールドです。
あなたのクリエイティブが社会に必要とされていると信じて、ぜひ一歩を踏み出してみてください。








コメント