公務員の中でも注目されている「デザイン職・クリエイティブ枠」。とはいえ、
「事務系の職種なのに、デザインスキルが求められるってどういうこと?」
「面接でどんな質問をされるの?」
と不安に思う方も多いはずです。
この記事では、デザイン職(事務系)の面接において出やすい質問例や、回答のポイント、実際に合格するための準備方法を徹底解説します。
「民間とは違う公務員デザイン職」の視点を押さえたうえで、あなたの経験やスキルをどうアピールするべきか、具体的にお伝えします。
公務員のデザイン職(事務系)とは? 求められる役割を再確認

公務員のデザイン職(事務系)は、自治体や行政機関において、広報物やデザイン関連の業務を担う専門職です。
しかし、その実態は「制作だけ」ではなく、事務的な要素と企画的な視点を融合させた、非常に多面的な役割が求められるポジションです。
単なるグラフィック制作だけでなく、地域の特性や行政の意図を的確にくみ取り、それを“誰にでも伝わる形”で表現する力が求められます。
特に公共性・公平性・住民視点に立った情報設計ができるかどうかが評価の分かれ目になります。
そもそも「デザイン職の事務系」とはどういう仕事?
デザイン職と聞くと「制作業務」がメインに思えるかもしれませんが、公務員の事務系デザイン職は、あくまで事務職の一つです。
具体的には、以下のような業務を担います:
- 広報誌・ポスター・チラシの作成
- SNS運用や動画編集
- ホームページ管理や更新
- デザインガイドラインの整備
- 地域イベントの企画・運営
つまり、単に手を動かして作るだけでなく、「行政目的に合致した広報設計」や「関係者との調整力」が求められる職種です。
また、時には行政施策の一環として、住民説明会用の資料をデザインしたり、アンケートの視認性を高めたりと、きめ細やかな対応が必要とされます。
民間のデザイナーとは違う視点が求められる
民間デザイン職は商品やサービスの売上向上を目指しますが、公務員のデザイン職はといった視点が求められます。
- 住民への情報伝達
- 公共性
- 平等性
- 長期的な行政施策との整合性
そのため、「美しい」「オシャレ」だけでは評価されず、“誰にでも伝わるか”、“地域課題に対応しているか”が重視されます。
たとえば、視覚障がいのある方への配慮、高齢者や外国人住民にも分かりやすいレイアウト、専門用語の回避など、制作におけるあらゆる配慮が求められます。
これはまさに、「伝えることのプロ」としての自覚が問われる職務であり、その点で民間のデザイン職とは大きく異なるアプローチが必要です。

面接でよくある質問と意図【7選】

公務員のデザイン職における面接では、一般的な事務職とも異なり、
「公共性の理解」
「デザイン力と調整力のバランス」
「行政で働く意義」
などを確認される傾向があります。ここでは、頻出する7つの質問とその意図、それぞれの回答ポイントと例文を紹介します。
回答内容を自分なりに落とし込むことで、より説得力のある受け答えができるようになるはずです。
Q1:「なぜ民間ではなく、公務員のデザイン職を志望するのですか?」

意図: 価値観のマッチング。利他的志向があるか?
回答のポイント
- 民間での経験を活かして、地域や社会に貢献したいという視点を示す
- 安定志向ではなく、「公共性」や「使命感」をアピール
回答例
民間企業でデザイナーとして働く中で、地域の課題解決に取り組む仕事に強く惹かれるようになりました。公務員として、行政施策に直結する広報や啓発に関われる点にやりがいを感じ、志望しました。
Q2:「公務員の中でも、なぜ“デザイン職”なのですか?」

意図: 自己理解の深さと志望動機の明確さ。
回答のポイント
- 公務員の中であえて“デザイン”を選ぶ理由を明確にする
- 自分の得意分野と行政ニーズの接点を語る
回答例
自治体の情報発信は、住民にとって大きな影響力を持つと感じています。私はデザインを通じて“伝える力”を培ってきたため、それを行政の広報に活かすことが自分にとって最も価値ある役割だと考えました。
Q3:「チームで制作物を進めた経験はありますか?」
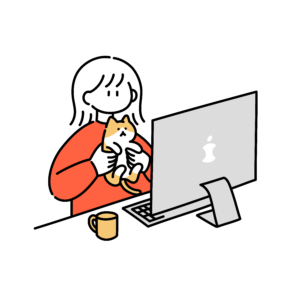
意図: 組織で働く姿勢、協調性。
回答のポイント
- 制作物は個人で完結しないことを理解しているかを示す
- チームでの分担や調整の工夫を語る
回答例
イベント告知ポスターを制作する際、他部署と連携しながら情報収集や原稿確認を行いました。相手の要望と制作スケジュールの調整を行う中で、調整力の大切さを学びました。
Q4:「デザインを通じて地域にどんな貢献ができると思いますか?」

意図: 公共性への理解。住民視点があるか。
回答のポイント
- 住民が“行動できる情報”をつくる意識を伝える
- 行政施策との接続を意識したデザイン観を持っているか
回答例
例えばごみ分別の啓発チラシでは、視認性や文字サイズを工夫することで、高齢者にも分かりやすい設計にしました。そうした小さな工夫が地域全体の行動変容につながると考えています。
Q5:「事務作業とデザイン、どちらの方が得意ですか?」

意図: バランス感覚。事務職としての自覚。
回答のポイント
- デザイン一辺倒ではなく、事務職としての責任感を示す
- バランスよく取り組む姿勢を伝える
回答例
どちらも大切だと考えています。制作の質を上げるためには、正確な事務処理や情報整理も欠かせないため、業務全体を俯瞰しながら対応できるよう意識しています。
Q6:「あなたにとって“良いデザイン”とは何ですか?」
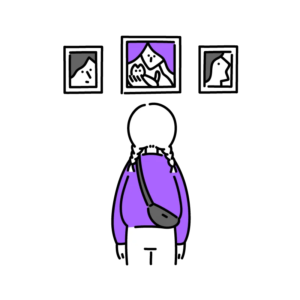
意図: 設計思考と価値判断。
回答のポイント
- 美的価値よりも“機能性”や“目的達成”を重視していることを示す
- 利用者視点や公共性を含めて語る
回答例
誰が見ても理解でき、行動に移しやすいことが“良いデザイン”だと思います。行政では、特に“分かりやすさ”や“誤解のなさ”が重要だと考えています。
Q7:「これまでのポートフォリオで、一番伝えたい作品はどれですか?」
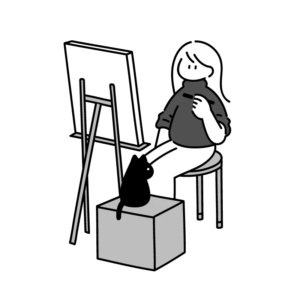
意図: 実績のアピール力と説明力。
回答のポイント
- 選んだ理由と制作の目的・背景を明確にする
- 成果だけでなく“配慮や工夫”のプロセスも語る
回答例
地域イベントの告知チラシを制作した事例です。幅広い年齢層を意識し、フォントや色使いに配慮しました。結果的に来場者数の増加にもつながり、反響を得ることができました。
回答のポイントと構成例【志望動機・自己PR編】

面接の中でも特に重視されるのが「志望動機」と「自己PR」です。ここでの受け答えが、あなたの“適性”と“再現性”を判断する大きな材料になります。
特にデザイン職の場合、単なる「デザインが好き」「制作が得意」では不十分です。行政というフィールドで「なぜ自分が必要とされるのか」をロジカルに伝える必要があります。
志望動機を伝える際の基本構成
- 結論(なぜ志望するのか)
- 理由(背景や価値観)
- 経験(具体的な実績)
- 今後の展望(どのように貢献したいか)
この構成を意識すると、面接官にとって“聞きやすく”“納得感のある”ストーリーになります。
例:
私は「地域課題を伝えるためのデザイン」に強く関心があります。民間で培った制作スキルを、行政の広報活動に活かしたいと思い、公務員のデザイン職を志望しました。これまで、地域イベントのチラシや啓発資料の制作を担当し、相手の意図を汲み取った設計を心がけてきました。今後は、住民の立場に立った“伝わる広報”を、行政の中で実現していきたいと考えています。
自己PRで押さえたい3つの観点
自己PRでは、自分の強みを一方的にアピールするのではなく、
「どのような業務でその強みを発揮できるのか」
「どのように貢献できるのか」
をセットで語ることが大切です。特に次の3つの観点を意識しましょう。
- 制作スキル(使用ソフト、レイアウト力、情報設計)
- 調整力(他部署との連携経験、納期管理)
- 公共性(利用者視点、社会的な配慮)
例:
私は、制作力と調整力の両面を強みとしています。デザイン事務所で制作担当をしながら、クライアントとの進行管理を担当してきました。特に、行政広報物の受託業務では、高齢者や子育て世代など幅広い層を意識した紙面設計を行い、分かりやすさを第一に心がけました。この経験を通じて「相手の意図を引き出す力」「分かりやすく伝える力」を身につけることができました。
ポートフォリオの扱い方と面接での見せ方

ポートフォリオは、あなたのスキルや経験を「視覚的に」伝える重要なツールです。しかし、見せる順番や話し方次第で、印象は大きく変わります。
単に「作品を見せる」だけでなく、
- 「どんな目的で作ったのか」
- 「誰に向けたデザインか」
- 「どのような成果を出したか」
まで説明できると、より説得力が増します。
見せる順番と説明のコツ
- 目的:何のための制作か
- 課題:どんな背景・制約条件があったか
- 解決策:どんな工夫をしたか
- 結果:どんな成果・反応があったか
※時間が限られる面接では、1作品あたり2~3分程度で説明できるように準備しておくのが理想です。
評価されやすい作品の特徴
- 地域性や公共性のある題材(自治体広報、啓発資料、案内掲示など)
- ユーザー配慮(フォントサイズ、色覚バリアフリーなど)
- 絵やイラストよりも「伝達設計」の視点が強調されているもの
可能であれば、実在の自治体の課題を想定した“架空課題”に取り組み、それを提示するのも効果的です。

本番前にやっておきたい面接対策5つ

面接で緊張してしまうのは、準備不足や想定外の質問が原因です。以下の5つの対策を事前に行うことで、自信を持って本番に臨めます。
- 模擬面接(録画や他人との練習)
- 表情や話し方、間の取り方を客観視できる
- ポートフォリオの口頭説明練習(3分以内に要約)
- 「伝えたいこと」がブレないようにする
- 想定質問と回答準備(本記事を参考に)
- 自分の言葉でスムーズに話せるようにする
- 逆質問の準備
- 例:「これまでに職員の方が手がけたデザイン事例などを知ることはできますか?」
- 志望自治体の広報誌・SNS・制作物をリサーチ
- 実際のトーンや方向性を把握しておく
それぞれの準備を本試験前までに少しずつ対策をしておけば、直前に慌てることも無くなるでしょう。
合格に近づくための行動を今すぐ始めよう

公務員のデザイン職(事務系)は、「デザインができる事務職」ではなく、「行政施策をデザインの力で支える事務職」です。
面接ではその認識をもとに、公共性・協調性・貢献意識をアピールできるかがカギです。
この記事で紹介した質問や対策をもとに、あなた自身の経験を言語化し、「自分ならではの役割」を明確に伝えていきましょう。
不安がある人ほど、準備を重ねれば確実に差がつきます。
ポートフォリオの再構成、志望動機のブラッシュアップ、想定問答の整理など、今日からできることを一つずつ積み上げていきましょう。











コメント