「美大を出ていないとデザイナーになれないのかな?」
いまこの記事を読んでいる読者の方で、そんな不安を抱えている方も多いかと思います。
ですが、何も心配することはありません。
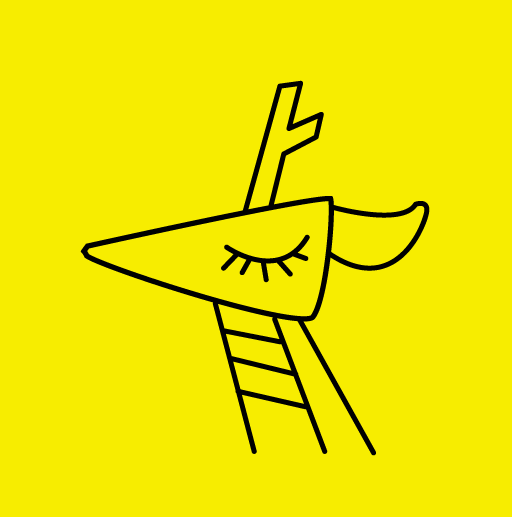 ぴりおど
ぴりおど僕自身、一般大学を卒業した後、就職せずデザイン専門学校へ通い、広告や紙媒体を中心としたグラフィックデザイナーとして働いてきました!
学び始めた当初は「やっぱり美大卒じゃないと厳しいかも」と感じていましたが、実際に就職してみると評価されたのは 学歴ではなくポートフォリオとスキル でした。
そして今は事務職をしながら、オンラインスクール「デイトラ」でWebデザインを学び直しています。
広告のデザインとは違い、WebではUI/UXやコーディングなど新しいスキルが必要です。
転職を目指すか、副業や自己研鑽で終わるかはまだ分かりませんが、「美大を出てなくても挑戦できる」 という実感は強まるばかりです。
今回の記事のポイントは以下の通り。
- 美大を出てなくてもデザイナーになれるのか
- 僕の実例(一般大学→専門学校→広告デザイナー)
- 社会人や学生が選べる3つの学び方
- Webデザインをオンラインで学ぶメリットと事例
過去、美大を出ていなくてもデザイナーになった僕自身の実体験を赤裸々に綴っていますので、ぜひ自分のキャリアを築く際の参考にしてみてください。
美大を出てなくてもデザイナーになれる?

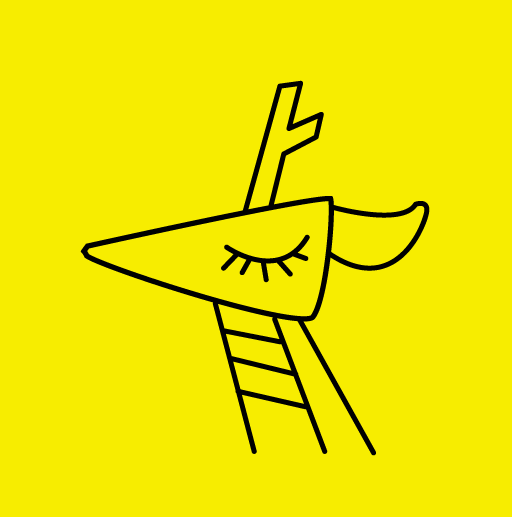 ぴりおど
ぴりおど結論から言うと、美大を出ていなくてもデザイナーにはなれます!
もし「美大を出ていないと不利なんじゃないか」と不安を抱いている方がいれば、僕は「そこまで心配する必要はありません」と断言できます。
なぜなら、実際に世の中を見渡してみると、主婦や会社員からデザイナーへ転身した人、まったく異業種からキャリアチェンジした人は数えきれないほどいるからです。
僕自身も美大ではなく一般大学を卒業し、その後デザインを専門的に学んでグラフィックデザイナーとして就職しました。
これは「美大卒でなくてもキャリアを築ける」という生きた証拠だと感じています。
では、美大卒と比較したときに、美大を出ていない人がどんな点で評価されるのか。ここを整理してみましょう。
美大の強みと就職でのメリット
確かに、美大には美大の強みがあります。
- 4年間をかけてデッサンや色彩理論などの基礎を体系的に学べる
- 周囲に優秀なクリエイター仲間が多く、刺激を受けながら成長できる
- 一部の大手企業や広告代理店では「美大卒」を採用条件にしているケースがある
そのため、美大卒の人材は「専門知識と技術がそろった即戦力候補」と見られやすいのは事実です。
ただし、これはあくまで「入口の評価」にすぎません。
就職してしまえば「美大卒かどうか」よりも「成果を出せるかどうか」がすぐに問われます。
学歴より評価される「ポートフォリオ」
デザイン業界の採用で最も重視されるのは、ポートフォリオです。
面接で必ず見られるのは「あなたがどんな作品をつくってきたか」「どのように課題を解決したか」という実例です。
これは僕自身の経験からも断言できます。
新卒でグラフィックデザイナーに応募したとき、採用担当者から聞かれたのは「大学名」ではなく、「このポスターはどういう意図でデザインしたの?」でした。
つまり、学歴ではなく“デザインの実力を証明する作品”が武器になるのです。
さらに今はSNSやポートフォリオサイトを通じて、未経験者でも自分の作品を公開できる時代です。
実際に「X(Twitter)やInstagramに上げた作品がきっかけで案件を受注した」という話もよく耳にします。
デザイン業界の採用基準の変化
ここ10年ほどで、デザイン業界は大きく変化しました。
紙や広告中心から、WebやアプリなどのUI/UXデザインが主流になり、求められるスキルも「絵が上手い」ことから「使いやすさや体験を設計する力」へとシフトしています。
そのため、美大卒かどうかは以前よりもさらに重要度が下がりました。
- Web制作会社やIT企業では「学歴不問・ポートフォリオ提出必須」が一般的
- 実力があれば、クラウドソーシングや副業からでも案件を獲得できる
- 未経験者を対象にした「オンラインスクール出身歓迎」の求人も増加している
むしろ「美大で学んだから安心」というよりも、「変化に対応して最新のスキルを身につけているか」が評価の基準になっているのです。
美大出てない僕がデザイナーになった実例

僕は一般大学を卒業したあと、就職せずにデザイン専門学校へ進学しました。
周囲が就職活動をしている中で、ひとりだけ「進路変更」を選んだのは、やはり心のどこかで「本当にやりたいのはデザインだ」という気持ちを抑えられなかったからです。
大学ではデザインと関係のない分野を学んでいましたが、在学中から広告やポスターの表現に強い関心があり、「自分もこんな仕事をしてみたい」と思うようになっていました。
社会に出てから後悔するくらいなら、まずは基礎からきちんと学び直そう。そう考えて専門学校への進学を決めました。
「美大以外」の進路を選んだ仲間たち
大学卒業後に通った専門学校の同級生の多くは高校を卒業してすぐに入学した人や、僕のように一般大学を経てから入学した人たちでした。
つまり、専門学校は「美大に行かなかった人の受け皿」でもあったのです。
だからといって、決してレベルが低いわけではありません。
むしろ、高校時代から自主的に作品を作り続けてきた人も多く、入学当初から完成度の高い課題を仕上げる同級生もいました。
「やっぱり美大出じゃないとダメなのかな」という不安は、ここでも顔を出しました。
ですが同時に「この環境でなら、自分も追いつけるかもしれない」という希望も感じました。
学び始めて感じた壁と気づき
入学当初は、やはり周りのレベルに気後れする日々でした。
高校時代からデッサンを描いてきた同級生の作品を見て、「自分は場違いなんじゃないか」と思ったこともあります。
しかし授業が進むにつれて、大きな気づきがありました。デザインは“絵の上手さ”だけで決まるものではないということです。
授業ではポスター制作や課題広告のデザインを行うことが多かったのですが、最も評価されたのは「情報が整理されていて、誰にでも分かりやすいデザイン」でした。
- たとえば、キャッチコピーをどう配置するか
- ターゲットが高校生か社会人かによって配色やトーンをどう変えるか
- クライアントの意図をどうビジュアルで表現するか
そうした“課題解決の力”がデザインの本質だと知ったとき、「美大を出ていない自分にも勝てる武器はある」と実感できました。
広告デザイナーとして働いた日々
卒業制作で作ったポートフォリオを武器に、僕は広告代理店系列の制作会社に応募しました。
面接では大学名の話はほとんど出ず、代わりに「このデザインはどういう意図で作ったの?」と作品について深く聞かれました。
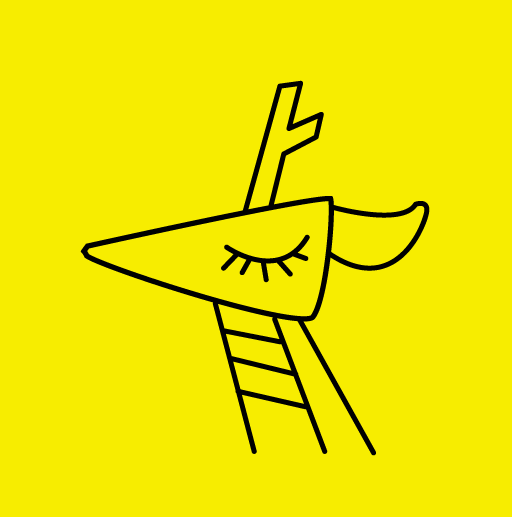 ぴりおど
ぴりおどその瞬間、「やっぱり評価されるのは学歴じゃなくて実力なんだ」と確信したのを覚えています。
無事に採用が決まり、広告・グラフィックデザイナーとしてのキャリアが始まりました。
最初はチラシやPOP、ポスターなど小さな案件を任されるところからスタートしましたが、徐々に販促キャンペーンや企業広告のデザインにも携われるようになりました。
現場での仕事は厳しい面もありました。納期に追われ、クライアントからの修正指示が一晩で何度も入ることも珍しくありません。
それでも、実際に自分の手がけた広告が街に貼り出されたり、クライアントに「分かりやすいデザインだね」と言われた瞬間には、何にも代えがたい達成感がありました。
この経験を通して僕は「美大を出ていなくても、努力と工夫次第でデザイナーとして活躍できる」と、強く実感しました。
美大を出てない人のための学び方3選

美大に行かなくてもデザインを学ぶ方法はいくつかあります。ここでは代表的な3つを整理し、それぞれのメリットと注意点を解説します。
- 専門学校で学ぶ
- 独学+発信
- オンラインスクールで学ぶ
順番に確認していきましょう。
専門学校で学ぶ
- 基礎から体系的に学べる
デザインの歴史、色彩学、タイポグラフィ、ソフトの操作などを幅広く学べます。特に基礎を一通りカリキュラムで習得できる点は強みです。 - 就職サポートが手厚い
学校と企業のパイプがあるため、求人紹介やポートフォリオの添削、面接対策まで支援が受けられるケースが多いです。 - 費用と時間の負担が大きい
2年で数百万円単位の学費が必要になる場合もあり、昼間通学すればアルバイトとの両立は難しいこともあります。
僕自身もこのルートで学びました。当時は「これが一番の近道」だと思っていましたし、確かに基礎を網羅的に学べたのは大きな収穫でした。
ただ、社会人経験を経てから振り返ると、「効率」という点ではもっと柔軟な選択肢があるとも感じます。
独学+発信
- 自由度が高い学び方
本やYouTube、ブログ記事などでインプットし、自分で作品を作って発信していくスタイル。誰に縛られることもなく、自分のペースで進められるのが魅力です。 - 自己管理力が必須
ただし、学び方や進度を自分で決めなければならないため、モチベーション管理が最大の課題。挫折する人が多いのも事実です。 - 発信が案件につながる可能性も
X(Twitter)やInstagram、ポートフォリオサイトに制作物を継続して公開することで、個人から案件を依頼されるケースも増えています。特にフリーランス志向の人には有効な方法です。
この方法は「費用をかけずに始められる」点で魅力的ですが、孤独な戦いになりがちなので、仲間を作ったり発信の習慣化が成功のカギになります。
オンラインスクールで学ぶ
- 社会人や学生に最も現実的
通学不要なので、仕事や学業と両立しやすい。夜や休日を使って受講できるのは大きなメリットです。 - 費用が専門学校より安い
10万〜30万円ほどで実践的なカリキュラムを受けられるスクールもあり、専門学校と比べると費用負担は軽めです。 - Webデザインに直結するスキルを効率的に学べる
PhotoshopやIllustratorだけでなく、Figmaやコーディングなど、現場で必要なスキルを「実務レベル」で学べるのが特徴です。
今の時代は、オンラインスクールが最短ルート と言えます。
特に「副業でデザインを始めたい」「本業を続けながらスキルを身につけたい」という人にとっては、時間・費用・効率のバランスが取れた選択肢です。
実際、僕も現在はオンラインスクールで学び直しており、「もっと早くこの方法を選んでいれば良かった」と思うこともあります。

Webデザインを学び直している理由

僕が今学んでいるのは「Webデザイン」です。以前はグラフィックデザイナーとして広告や紙媒体を担当していました。
チラシやポスター、会社案内などを作る仕事は好きでしたが、正直なところWebの知識はほとんどゼロでした。
デザイナー時代も、Web案件になるとコーダーや別のデザイナーに任せるしかなく、「自分は紙専門」という枠に閉じ込められていました。
ただ、転職して事務職に就いた今でも「やっぱりデザインを学び続けたい」という気持ちは消えませんでした。
むしろ、デザインの需要が紙からWebにどんどん移っている現実を見て、「今のままでは何も作れなくなる」という危機感が強まりました。
広告とWebデザインの違いに気づいた
広告デザインの現場では、とにかく「目立つこと」「印象に残すこと」が重要でした。
ポスターなら数秒で伝え切る力、キャッチコピーとビジュアルのインパクトが勝負。
一方でWebデザインを学び始めてから気づいたのは、まったく違う軸が必要だということです。
Webでは、華やかさ以上に 「使いやすさ」「わかりやすさ」「目的達成までの導線」 が問われます。つまり、UI/UXという考え方が根底にあるんですね。
たとえば広告なら「いかに買いたくなるか」を考えますが、Webでは「ユーザーが迷わず目的のページにたどり着けるか」「ストレスなく情報を得られるか」が重要。
学び直して最初に突き当たったのは、この意識のギャップでした。
「デザイン=見た目を良くすること」ではなく、「ユーザーの体験を設計すること」。この気づきは、僕にとって衝撃的でした。
社会人に最適な学び方
じゃあ、どうやってそのギャップを埋めるか。
社会人になった今、もう一度専門学校に通うのは現実的ではありません。費用も時間もかかりすぎるし、フルタイムで働きながらでは到底無理。
そこで選んだのが、オンラインスクール「デイトラ」でした。
- 通学不要:仕事終わりや休日に、自分のペースで学習できる
- 価格が専門学校より安い:数十万円規模の投資で済む
- 現役デザイナーからのフィードバック:課題を提出するとプロの視点で添削してもらえる
この環境が、自分のように「もう一度デザインを学び直したい社会人」にぴったりだと感じました。
実際に受講してみると、単なる動画教材ではなく「課題→提出→フィードバック→改善」というサイクルがあるおかげで、独学よりもはるかに実践的にスキルが身につきます。
僕にとってデイトラは、単なる“学習の場”ではなく、再びデザインと向き合うための“再スタートの場所”となりました。
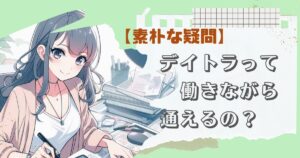
スクールで学んでデザイナーになった事例

実際にオンラインスクールからデザイナーになった人はたくさんいます。ここでは、僕が受講しているデイトラの受講生の具体例を紹介します。
フリーランスとして案件を獲得した例
- 育児と両立しながら半年で初案件→フリーランス
2児のママがWebデザインを学び、受講開始から約半年で初案件を受注。その後はフリーランスのWebデザイナー&ライターとして活動を拡大しています。
(参考:2児のママが未経験からWebデザインを学び、受講開始から半年で初案件を受注!? スキマ時間×時短家事で実現したフリーランスデザイナー&ライターの二刀流生活とは? – デイトラ情報局) - 事務職から学び直し→3社と業務委託で在宅フリーランス
元事務職の受講生がWebデザイン&営業支援を受講後、3社と業務委託契約を締結。在宅で理想の働き方を実現し、単価も事務時代から大幅アップ。
(参考:元事務職員が未経験から Web デザインを学び、フリーランスとして独立⁉ 体が弱くても在宅で輝けるWeb系キャリアの作り方とは? – デイトラ情報局)
いずれも、主婦や普通の事務職からフリーランスになった受講生の実例となっています。
転職に成功した例
- 元派遣社員→就活開始から1.5か月で正社員Webデザイナー内定
Webデザイン/制作/転職支援をトリプル受講し、転職活動1.5か月で正社員Webデザイナーの内定を獲得。
(参考:元派遣社員が就活開始から1.5か月で未経験からWebデザイナーに内定!? 転職を成功させた秘策とは? – デイトラ情報局) - 人事職から制作会社の正社員Webデザイナーへ
学習を経て、就活開始から約1.5か月で地元制作会社に内定。入社後は正社員デザイナーとして活躍中。
(参考:未経験からWebデザインを学び制作会社の正社員デザイナーに!? 転職活動開始から1か月半で転職成功した秘訣とは? – デイトラ情報局)
2人ともWebデザインを学んだ後、わずか1.5か月でWebデザイナーへの転職を成功させています。
これらの事例からも分かるように、オンラインスクールは学びながら実務に近い経験(課題→ポートフォリオ→案件/選考)を積めるのが大きな強みです。
コミュニティや添削も後押しになり、未経験者でも挑戦しやすい環境が整っているのがわかりますね。
\ 知名度もあって、コスパも抜群! /
よくある質問(FAQ)

ここから、デザイナーを目指すにあたってのよくある質問をまとめました。しっかりとチェックして、不安な要素を一つずつ無くしていきましょう。
Q. 美大でなくてもデザイナーになれる?
A. なれます。
実際に美大を出ていないデザイナーは業界に数多く存在します。
評価されるのは学歴よりもポートフォリオの完成度や実務で使えるスキルです。
採用担当者は「どんな大学を出ているか」よりも「この人に仕事を任せられるか」を見ています。
特にWebデザイン分野では、美大卒かどうかはほとんど問われません。
Q. 社会人でもデザイナーを目指せる?
A. 可能です。むしろ社会人経験が強みになることもあります。
社会人として培った「コミュニケーション力」「ビジネス理解」はデザイナーとして大きな武器です。
また、今はオンラインスクールや副業案件が普及しており、働きながらスキルを学ぶ環境が整っています。
たとえばデイトラやデジハリのようなスクールなら、夜や休日に学習を進めながら転職や副業を目指せます。
Q. デザインのセンスがなくても大丈夫?
A. 大丈夫です。センスよりも“考え方”が重要です。
デザインにおける「センス」とは生まれつきの才能ではなく、知識と経験から磨かれる力です。
実際の仕事では「情報を整理して分かりやすく伝える力」や「ユーザーにとって心地よい導線を作る力」が求められます。
これらは学習と実践を重ねることで確実に身につけられるスキルです。
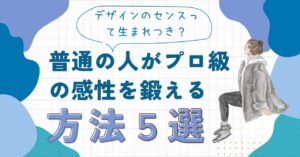
Q. 副業でもデザインを始めるのは可能?
A. もちろん可能です。
最初はバナー制作やLP(ランディングページ)のデザインといった小さな案件から始められます。
クラウドソーシングやSNSを活用すれば、未経験でも受注のチャンスは十分あります。
実際に「本業は事務職だけど、副業で月5万〜10万円を安定して稼げるようになった」というデイトラ卒業生の事例も出ています。
心配無用!美大を出ていなくてもデザイナーになれる

僕自身の経験から断言できます。美大を出ていなくても、デザイナーにはなれます。
一般大学を卒業後に専門学校で学び、グラフィックデザイナーとして働いた経験。
そして今は、オンラインスクールでWebデザインを学び直している経験を通じて強く感じるのは、評価されるのは学歴ではなく「スキル」「作品」「挑戦する姿勢」だということです。
実際にデイトラなどのオンラインスクールから、未経験の主婦や異業種の社会人がフリーランス・転職に成功している例は数多くあります。
つまり「やりたい」と思ったときが、挑戦を始める一番のタイミングです。
かつては専門学校や美大しか選択肢がありませんでしたが、今はオンラインスクール・独学・副業という柔軟な学び方が存在します。
自分のライフスタイルに合わせた方法で、スキルを積み上げていけるのです。
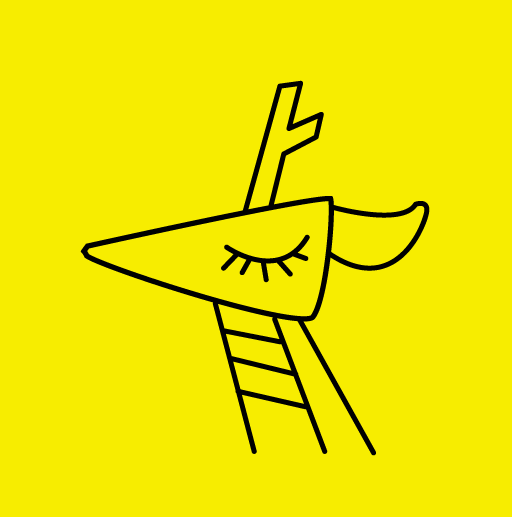 ぴりおど
ぴりおどもし「美大を出ていないから無理だ」と迷っているなら、それは思い込みにすぎません!
むしろ、未経験でも挑戦できる時代に生きているのは大きなチャンスです。今日からできる小さな一歩を踏み出してみましょう。
- 本を一冊読む
- 無料デザインツールでバナーを作ってみる
- オンラインスクールの体験講座を受けてみる
小さな行動の積み重ねが、未来のキャリアを大きく変えていくのです。
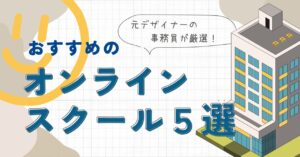
\ 知名度もあって、コスパも抜群! /
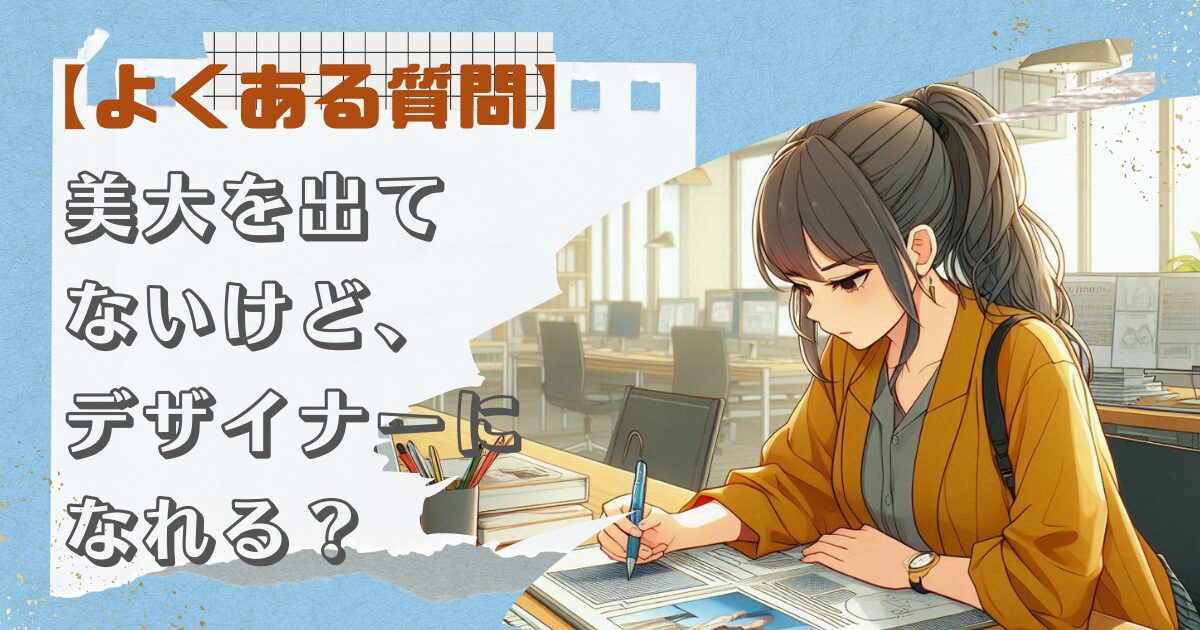


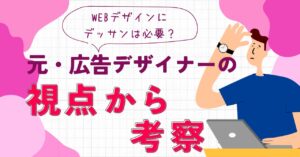
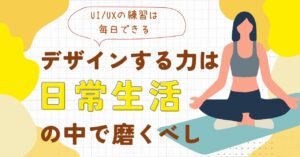
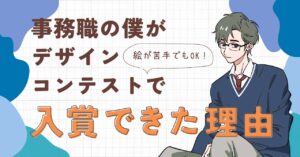
コメント