公務員のデザイン職や広報担当職を目指す方にとって、「志望動機」は面接やエントリーシートの中でも特に重要なポイントです。
「なぜ行政の広報やデザインに関わりたいのか?」
「民間と何が違うのか?」
——この問いに対して、明確で説得力ある言葉で応えることができれば、あなたの魅力はぐっと高まります。
今回は、そんな志望動機を磨くためにおすすめの書籍を5冊ご紹介します。
どれも“伝えることの本質”に触れられる内容で、公務員デザイン職を目指す方にぴったりの選書です。
なぜ“本”を読むと志望動機が強くなるのか?|3つの理由

志望動機を考えるとき、多くの人が「自分の経験」や「身の回りの出来事」から理由を組み立てます。
それはとても自然なアプローチですが、どうしても表現が似通ったり、説得力に欠けたりすることがあります。
そこで、本を読むことが効果的な理由を3つの視点で紹介します。
1. 他者の視点に触れることで、考えの幅が広がる
本には自分では考えつかないような視点や価値観が詰まっています。
他者の思考フレームに触れることで、自分の視点が客観化され、志望動機の内容にも深みが出ます。
2. 志望動機に“根拠”が生まれる
「このテーマに興味を持った理由」や「こういう仕事をしてみたい」といった思いに、書籍の内容を根拠として添えることで、面接官に納得感を与えることができます。
読書を通じて得た知識や実例を交えると、説得力が格段に上がります。
3. 自分の言葉で話せるようになる
本を読むことで言語のストックが増えます。
特に、自分の考えを言語化するのが苦手な人にとっては、読書が“言葉を磨くトレーニング”になります。これは面接やエントリーシートで非常に役立ちます。
以下では、そんな“言語化の補助線”になるおすすめ書籍を紹介していきます。
志望動機に効く!おすすめデザイン本はこの5冊

まずは結論から。公務員の広報・デザイン職を目指す方におすすめの5冊はこちらです:
- 『デザイン思考が世界を変える』[アップデート版](ティム・ブラウン著)
- 『なるほどデザイン』(筒井美希 著)
- 『伝わっているか?』(小西利行 著)
- 『自治体広報のすごい仕掛け』(河井孝仁 著)
- 『行政×デザイン 実践ガイド』(中山郁英 著)
ここからは、それぞれの本がなぜおすすめなのか、どんな学びがあるのかを詳しく紹介していきます。
それぞれが、伝える力を磨き、志望動機を深めるためのヒントにあふれた一冊です。
おすすめ本①『デザイン思考が世界を変える』[アップデート版](ティム・ブラウン著)
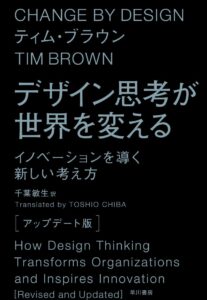
デザインコンサルタント会社、IDEO(アイディオ)のCEOである著者が企業や行政における「デザイン思考」の可能性を解説した一冊。
「問題解決の手法としてのデザイン」を提唱し、ユーザー視点から課題を捉え、形にするまでのプロセスを丁寧に解説しています。
この本から得られる学び:
- 住民目線での課題発見と解決の手法
- 行政における“共創”の考え方
- 広報=一方通行ではない、という意識改革
志望動機例:「住民との共創を意識した行政デザインに取り組みたい」などの裏付けとして有効です。
実際に行政サービスの改善や、まちづくりに応用されている実例も多く紹介されているため、具体性を持った志望動機に深みを加えることができます。
おすすめ本②『なるほどデザイン』(筒井美希 著)
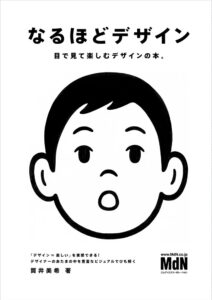
“見てわかる、読んで納得”をコンセプトにした、視覚的にわかりやすいデザイン解説書。
デザインの基本原則から、視線誘導、文字と余白の使い方まで、広報物の制作に直結する知識が詰まっています。
この本から得られる学び:
- 情報整理・視線誘導の基本
- 行政広報にも通じる「見やすさ」と「わかりやすさ」
- ビジュアルで“誤解なく伝える”という発想
ポスターやチラシなど、ビジュアル広報が重視される自治体の採用試験では、「デザインの意図」を語る場面も出てきます。
面接で「どうしてその配色にしたの?」「そのフォントを選んだ理由は?」と聞かれても、この本の知識があれば論理的に答えられるようになります。
おすすめ本③『伝わっているか?』(小西利行 著)
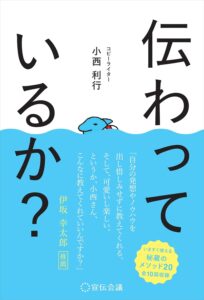
現役コピーライターの著者が「伝え方の極意」をやさしい言葉でまとめた実用書。
論理より“気持ち”が先に立ってしまいがちな志望動機や自己PR文を、ぐっと引き締めてくれる一冊です。
この本から得られる学び:
- 書類選考を突破する「短く強い言葉」の作り方
- 説得力ある自己PR文のテンプレート感覚
- 面接で伝えきれなかった“熱意”を整理する方法
「想いはあるけど、うまく言葉にできない」──そんな人に特におすすめです。
筆記は得意でも、面接で想いが伝えきれないという悩みのある方にとって、“言葉の筋トレ”になる本です
おすすめ本④『自治体広報のすごい仕掛け』(河井孝仁 著)
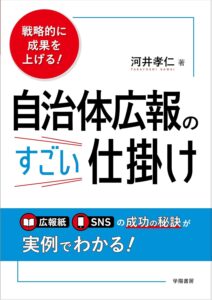
地方自治体の広報戦略や、住民の心を動かす伝え方にフォーカスした一冊。
具体的な成功事例や、広報活動にまつわる創意工夫が豊富に紹介されています。
この本から得られる学び:
- 行政広報における“しかけ”の考え方
- 実践されている全国の自治体事例
- 住民との関係性を築くためのデザイン的視点
「行政でなぜデザインなのか?」
という問いに対して、広報現場の実例を通して、より実践的で説得力のある志望動機を組み立てる助けとなる一冊です。
おすすめ本⑤『行政×デザイン 実践ガイド』(中山郁英 著)
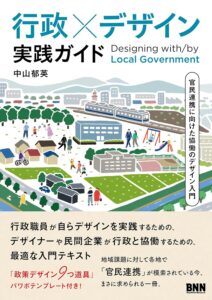
地方自治体の現場で実際に取り組まれているデザイン活用の事例を、実践者の視点から紹介したガイドブック。
政策立案や広報だけでなく、住民参加型プロジェクトなど、行政とデザインの接点を多面的に捉えています。
この本から得られる学び:
- 実際の自治体で行われたデザインプロジェクトの事例
- 行政内部でデザイン思考を導入する手法
- 「行政でなぜデザインか?」という問いへのリアルな答え
理想論ではなく、現場に根ざした知見が得られるため、説得力ある志望動機や面接対応に直結する内容です。
読書のあとに得られる“変化”とは?
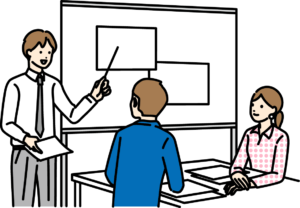
これらの本を読んだあとに得られる最大の変化は、「自分の想いを、相手に伝わる形で表現できるようになる」ことです。
志望動機や自己PRで陥りがちな“主観的すぎる言い回し”や“説得力の欠如”を、本の中にある知見や言語化の技法が補ってくれます。
また、行政の広報・デザインという業務についても、感覚や憧れではなく、実際の取り組みや社会背景を踏まえて語れるようになります。
採用担当者からも「この人は現場を理解している」「入庁後のイメージが持てる」と信頼されやすくなります。
さらに、“言葉にしたことで自分の方向性がよりクリアになる”という副次的な効果もあります。
読書を通して自分の価値観や思考のクセを客観視できるようになり、「自分はなぜこの職を目指すのか?」に対する納得度も高まります。
読んで終わりではなく、読んだことを自分の言葉に変えて、声にして、紙に落とし込む──その過程が、あなた自身の“伝える力”の基礎となっていきます。
まとめ|読むことで、言葉に説得力が宿る

どの本も、ただ「知識を得るため」だけでなく、「自分の想いを言葉にするため」のヒントが詰まっています。
広報やデザイン職を志望する中で、「自分の気持ちはあるけれど、それをどう伝えればいいか分からない」と感じたことはありませんか?
今回ご紹介した書籍は、そうした“もどかしさ”に寄り添い、あなたの志望動機を深め、言葉に変える手助けをしてくれます。
また、本を通じて広報やデザインの仕事の奥行きや現場のリアルを知ることで、「本当にこの仕事がしたい」と思える自信にもつながるはずです。
志望動機が固まっていない人、書いてみたけど何かしっくりこない人こそ、ぜひ手に取ってみてください。
この一歩が、あなたの言葉を強くし、未来を引き寄せる力になるかもしれません。









コメント