 悩む人
悩む人デザインって、特別な才能がいるんじゃないのかしら?
 悩む人
悩む人僕にはセンスもソフトの知識もないし…
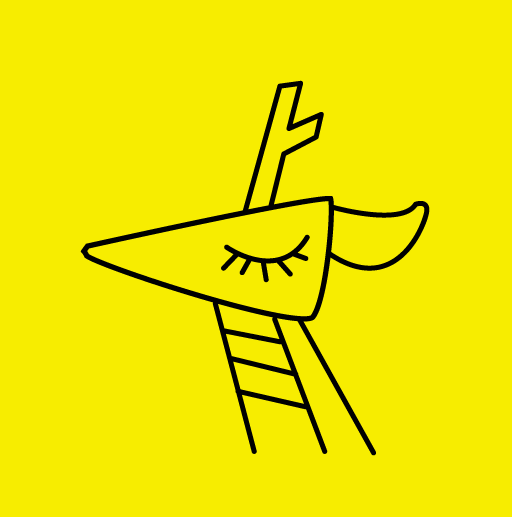 ぴりおど
ぴりおどそんなふうに思ってる人にこそ僕は伝えたい。 “デザイン脳”は、日常の中でじわじわ育てられるということを…!
デザインの勉強というと、美術館に行ったり、本を読んだり、難しいソフトを使いこなしたり…そういった部分にフォーカスされることが多いですよね。
でも実は、普段の行動の中に 「伝える力」「整える力」「選ぶ力」など、デザインの基本要素がたくさん潜んでいます。
さらに、デザイン脳は日々の生活の中で少しずつ意識的に育てることができます。
今回の記事では、デザイン未経験者でも自然とデザイン脳を育てることのできる「日常のルーティン20選」を紹介します。
日常生活の中で今回のルーティンを少しずつ取り入れていけば、いつの間にか驚くほどデザイン力がアップしていることに気付くでしょう。
デザイン脳を育てる日常ルーティン20選

早速、日常のルーティンの中でできるデザイン脳の育て方を20個、ご紹介します。
- 洋服のコーディネートで配色を感じる
- 冷蔵庫の中を使いやすく整える
- パッケージデザインを見て商品を選ぶ
- 手帳やノートを色分け・整理する
- スマホアプリで「UXの違い」に気づく
- SNS投稿の写真を整える
- インテリアで空間の見せ方を意識する
- 料理やお弁当の盛り付けを彩りよくする
- 掃除や片付けをエリアごとに進める
- ToDoリストを見やすく整える
- ラッピングで見た目の演出を楽しむ
- 買い物リストをカテゴリ別にまとめる
- 持ち物リストで使用シーンを想定する
- フォルダやデスクトップを整理する
- 家族用メモや掲示物を“見やすく”作る
- 名刺や案内状のレイアウトにこだわる
- 棚や引き出しにラベルを貼って分類する
- 話の順番や説明の構成を考える
- 写真アルバムをテーマごとに整理する
- 洗面台やキッチンで“動線”を整える
いずれも日常生活の中で簡単に実践できるものばかり。1つずつ具体的に見ていくことにしましょう。
洋服のコーディネートで配色を感じる

「今日はこのシャツに何を合わせよう?」 服を選ぶとき、私たちは自然と色のバランス、全体のまとまり、シルエットを考えています。
これは、グラフィックやWebの世界でいう「配色設計」や「構成設計」そのものです。
さらに、「初対面の人と会うから落ち着いた色にしよう」とか「プレゼンの日だから信頼感を出したい」と考えるのは、デザインの本質である“相手目線”を体現している行為。
つまり、TPOを意識したコーディネート=ビジュアルコンセプト設計なのです。
冷蔵庫の中を使いやすく整える

使いたい食材がすぐ見つかる、取り出しやすい配置になっている冷蔵庫。
これ、まさに“UI(ユーザーインターフェース)”の設計と同じです。
例えば、よく使う調味料をドアポケットに、消費期限の短いものを手前に。
この“迷わず使える”構造は、Webサイトのナビゲーション設計と同じ考え方。
冷蔵庫整理は、生活の中のユーザビリティ・テストと言ってもいいかもしれません。
パッケージデザインを見て商品を選ぶ

同じ中身なのに、つい高そうなパッケージを手に取ってしまった経験、ありませんか?
それは、あなたが視覚デザインの効果に自然と反応している証拠です。
パッケージに使われている色、フォント、写真の印象、空白の取り方。
それらが「信頼感」「高級感」「親しみやすさ」を伝えているのです。
しかも、“あざとい演出”を見抜いて避けたことがあるなら、それはもう立派なデザイン的な目利き。
手帳やノートを色分け・整理する
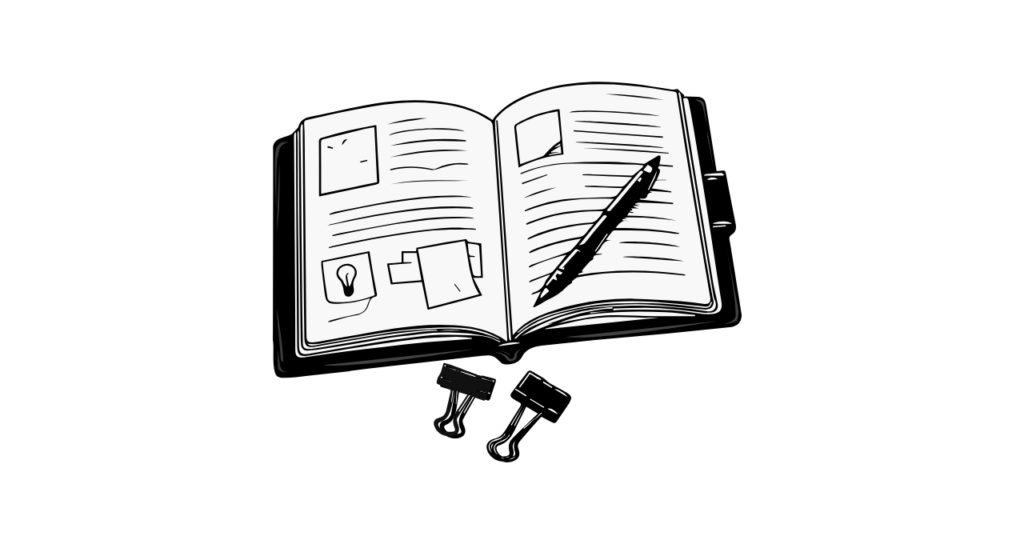
仕事・プライベート・趣味の予定を色分け。 メモには見出しや余白をつけて、あとから見返しやすいようにする。
これ、デザインの基本中の基本である情報整理と視覚構成です。
使う人(=自分)のために、「どんな形で書けば理解しやすいか」を考える。
それはまさにユーザー中心設計(UCD)の思考そのものです。
スマホアプリで「UXの違い」に気づく

「このアプリ、なんか分かりにくい」
「こっちは直感的に使えて気持ちいい」
そんな風に感じたことがあるなら、あなたの中にUXリテラシーが育ち始めています。
文字の大きさ、ボタンの配置、画面遷移のスムーズさ。
こうした設計に対して“違和感”を覚える力は、立派なデザインの素地。
気づけることが、デザインの第一歩です。
SNS投稿の写真を整える

明るさの調整、構図のトリミング、余白のバランス。
それを“なんとなく”でやってるあなたは、視覚編集のセンスを自然に鍛えているんです。
さらに、投稿文の改行や絵文字の位置、ハッシュタグの並べ方など、言葉の見せ方=テキストデザインもやってます。
SNSは、現代人の無意識デザイン訓練所です。
インテリアで空間の見せ方を意識する

家具の配置、照明の角度、観葉植物の置き場所。
これらを考えるとき、あなたは空間構成と視線誘導を自然とやっています。
「なんかここだけ窮屈に感じる」「もう少し広く見せたい」 この“なんか変”に気づく力が、デザイン脳の核心。
部屋づくりは、暮らしのUIをデザインすることでもあるんです。
料理やお弁当の盛り付けを彩りよくする

「赤が足りないからミニトマトを足そう」 「主菜が茶色だから、緑を挟もう」
これはもう完全に配色理論+構成美の世界。
味だけでなく、見た目で“美味しそう”を伝える技術は、グラフィックデザインと共通点だらけです。
食卓は、色彩感覚を磨く絶好のトレーニング場です。
掃除や片付けをエリアごとに進める

「今日は本棚だけ」「明日はキッチン」 段取りを立てて整頓していくのは、構造化思考×プロジェクト設計の発想です。
必要・不要を仕分け、使いやすい配置に戻す。
それはデザインにおける「情報の最適配置」と本質的に同じ作業です。
整理整頓は目に見えないデザインの訓練です。
ToDoリストを見やすく整える
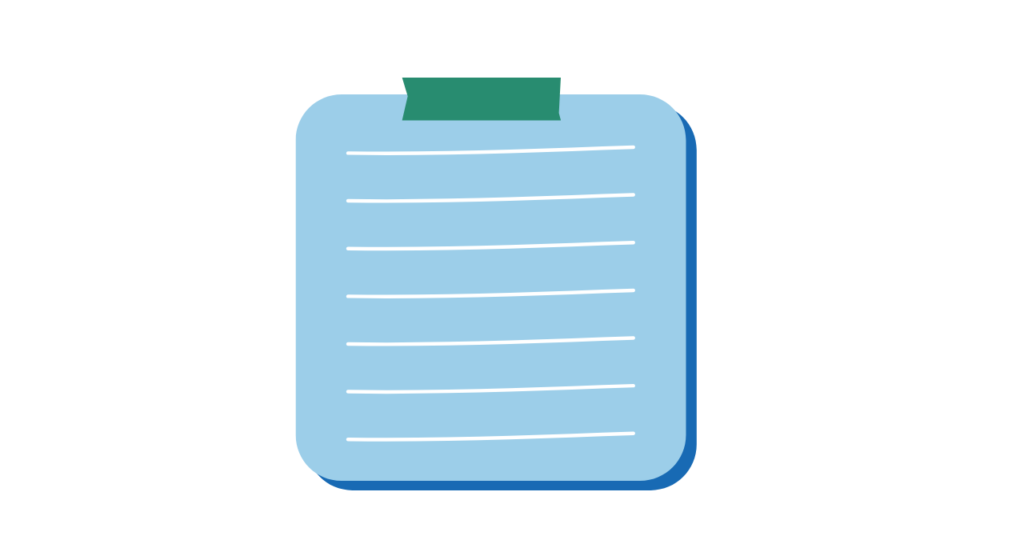
やることをカテゴリ別に分けて、優先順位を明確にして、チェックできるように整える。
この流れ、プレゼン資料の設計やインフォグラフィックとほぼ同じです。
視覚的に思考を整理する力=構造化スキル。 日常のメモが、そのままビジネスで活きる武器になります。
ラッピングで見た目の演出を楽しむ

包装紙、リボン、シール、箱のサイズ感。
開けた瞬間に相手が「わっ」となるように演出する行為は、完全にパッケージデザインです。
感情を動かすための見せ方、手触り、開封の流れまで含めた“体験設計”は、プロのデザイナーも日々考えている視点です。
買い物リストをカテゴリ別にまとめる

食品、日用品、文房具…とジャンル分けをして買い物メモを作る。 これはもう情報分類・階層設計です。
店内で迷わず買い物ができるというのは、構造化された情報が機能している証拠。
持ち物リストで使用シーンを想定する

「雨が降ったら…」「お土産を入れる袋も必要かも」 といった“状況を想定した準備”は、UXデザインにおけるユーザーの利用シーン設計と全く同じ。
想像力+構成力のかけ算が問われる場面です。
フォルダやデスクトップを整理する

「この書類はこのフォルダ」「プロジェクトごとに色分け」など、視覚的にわかる分類をしている人は、ナビゲーション設計の基礎をすでに実践中です。
フォルダ構成のセンスは、Webデザインや情報アーキテクチャにも直結します。
家族用メモや掲示物を“見やすく”作る
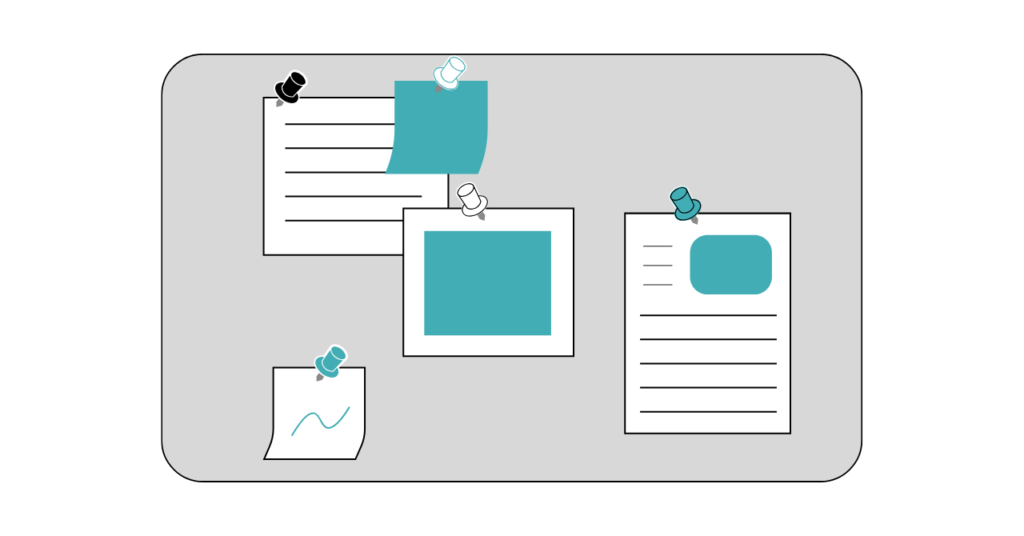
「ゴミ出しの日」を大きな文字で書く、カラフルに区分けする、イラストを入れて目立たせる。
これはもう完全に視覚的コミュニケーションのデザインです。
“伝える相手”を意識して形を工夫する=立派なデザイナー的思考。
名刺や案内状のレイアウトにこだわる

右寄せにしてみる、余白を少し広げてみる、色の濃さを落とす。
こういった微調整を「なんとなくやってる」人は、見た目の違和感に気づく力=デザイン感度が備わっています。
棚や引き出しにラベルを貼って分類する

モノに“名前”を与えて整理する行為は、情報をアイコン化する発想に近い。
ラベルの色や形、位置まで工夫できれば、視認性の高いインターフェース設計にもなります。
話の順番や説明の構成を考える

「結論から話そう」「具体例を先に出そう」など、説明の順番を考える行為は、まさに情報構成のスキルです。
これはプレゼンや資料作成、企画書づくりにも通じる、“見せ方”の根幹になります。
写真アルバムをテーマごとに整理する
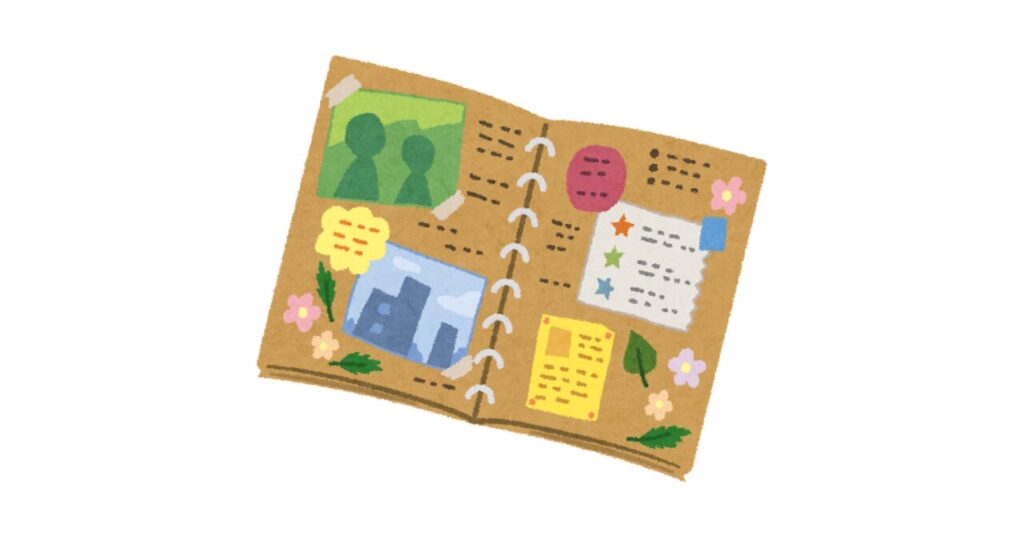
イベントごと、人物ごと、時系列に分けるなど、コンテンツ編集の思考が必要になります。
「ストーリー性を持たせたい」と思った瞬間、あなたはすでに構成演出の世界に踏み込んでいます。
洗面台やキッチンで“動線”を整える
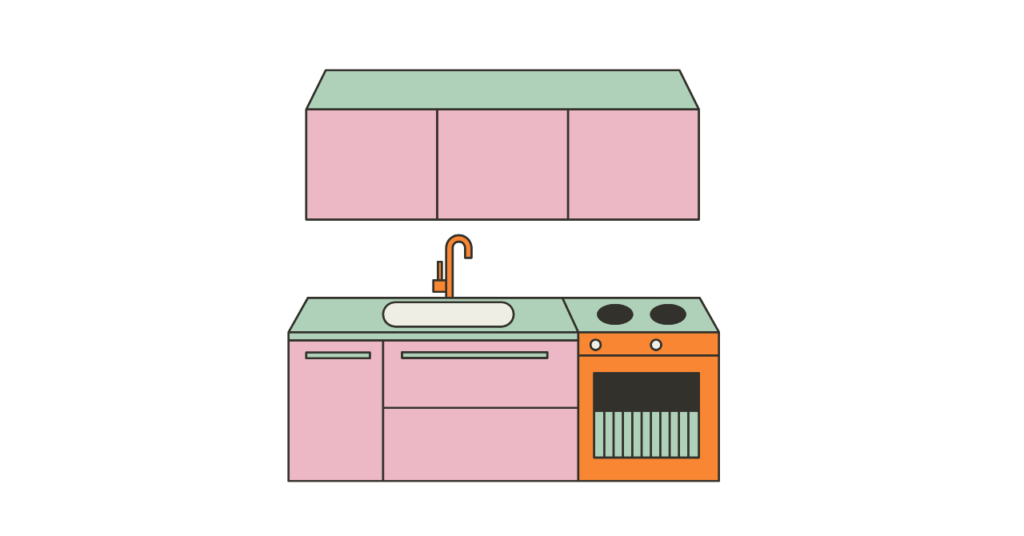
使う順にモノを並べたり、よく使うアイテムを取り出しやすく配置するなどの工夫。
これこそ生活導線=UX設計です。
「どうすれば無駄な動きが減るか?」「ストレスを感じないか?」という視点が、デザイン的価値を生み出します。
デザイン脳は日常を丁寧に見る目から育つ

ここまで見てきたように、デザイン脳は自分自身の日常生活を丁寧に見ていくことで育っていきます。
そんな日常生活を丁寧に見るヒントをお伝えします。
- 「なんか変」は、もう立派なセンス
- 違和感に理由をつけるクセをつける
- 比べることで、デザインの目が育つ
「なんか変」は、もう立派なセンス

僕は昔から、ポスターの行間が妙に詰まってたり、コンビニの棚の並びが微妙にズレてたりするのが気になるタイプでした。
もちろん、そんな“細かいとこ気にするなよ”って言われることもありましたが、なんというか、放っておけなかったんですよね。
でもこれ、今思えばデザイン的な感覚の芽生えだったんです。
「なんか変だな」と感じる、その小さなモヤモヤが、デザインにおける観察力のスタートライン。
プロのデザイナーだって最初はそこから始まります。
センスがある人って、何かを一発でパッと作れる天才ではなくて、「違和感」に敏感で、それを放っておかない人なんですよね。
違和感に理由をつけるクセをつける

「なんか変」をそのままにせず、「なんでそう感じたのか?」を言語化するクセをつけると、グンとレベルが上がります。
たとえば、「この広告、なんかダサい」と思ったとき。
色使い?文字の多さ?写真の切り方?レイアウトの詰め込み感?
一つひとつ可能性を探っていくと、自然とデザインの基礎知識が身についてきます。
僕自身、デザイン専門学校の頃はこれが大の苦手で、先生に何度も「理由を言語化して」って言われて苦しみました。
でも、訓練していくうちに、「説明できる」ってことが、実は一番のセンスかもしれないと思うようになりました。
つまり、「直感」から「根拠」へ。これが感覚をスキルに変えていく道なんです。
比べることで、デザインの目が育つ

僕が一番伸びたと感じたのは、“比較”を意識するようになったとき。
街にあふれるチラシや商品パッケージ、アプリやWebサイトのUIなど、「AとB、どっちがいい?」じゃなくて、「どっちを選んだか、なぜ選んだか?」に注目するようにしました。
たとえば、同じお茶でも、なぜこっちのパッケージに惹かれたのか。色?余白?文字の印象?
理由を掘り下げると、次第に「選ぶ目」が育ってきます。
これ、ほんとうに面白いくらい感覚が磨かれます。日常がデザインの教材に見えてきます。
小さな整える習慣が、未来のスキルになる
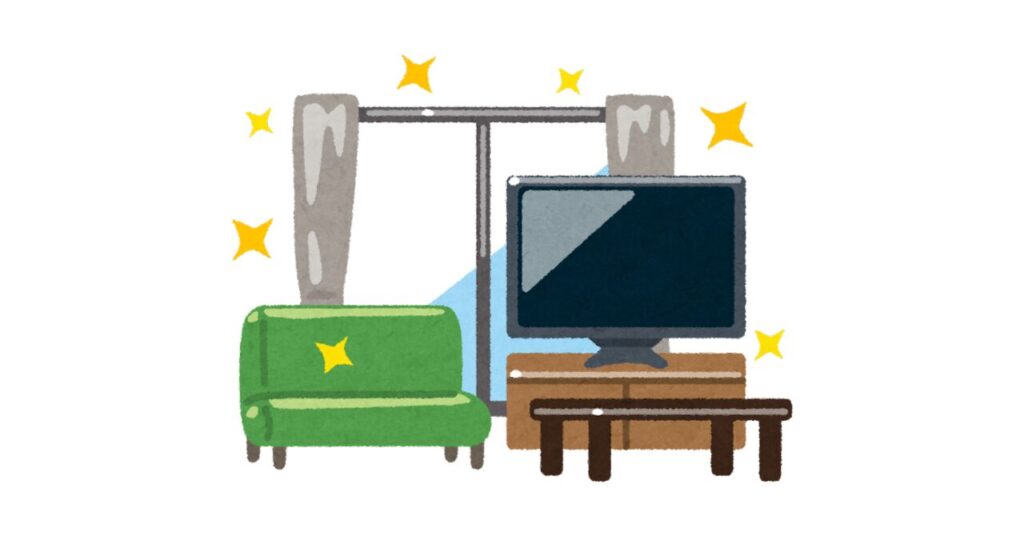
自分の身の回りをキレイにと整えることも、デザイン脳を育てるためには大事な行為です。
- 家の片付けが、まさかの情報設計
- 手帳の色分けはユーザー目線の訓練
- 洗面台を整えるは、朝のUXそのもの
家の片付けが、まさかの情報設計

僕は掃除がわりと好きで、休日になると「今日は本棚だけ」「来週は冷凍庫」といった感じで、エリアを分けて片付けています。
ある日それを見た友人に「それ、プロジェクトマネジメントじゃん」と言われて吹き出しました(笑)
でも本当にその通りで、範囲を決めて段取りを組んで、目的に向かって整えていくという思考は、まさに情報設計そのもの。
たとえば、資料をつくるときも同じで、構成を分けて、要点を整理して、無駄な情報を省く。
「片付け=思考の整理」なんですよね。つまり、整理整頓できる人って、それだけでデザインに向いてる素質があると思います。
手帳の色分けはユーザー目線の訓練

僕の手帳はカラフルです。青文字は仕事、緑文字はプライベート、赤ラインは締切。
一目見てわかるようにしてるんですが、実はこれ、「未来の自分=ユーザー」に向けた設計だったことに、あるとき気づきました。
「あとから見返す」ことを前提に情報を配置する。これはまさに、ユーザー中心設計(UCD)の考え方です。
さらに、余白のとり方、見出しの入れ方、書き込みのレイアウト。
こうした工夫を無意識でやっている人は、情報整理の才能があるかもしれません。もはや「手帳=人生のUI設計書」です(笑)
洗面台を整えるは、朝のUXそのもの

ある朝、何気なく洗面台の上を見て、「あれ?これ使う順に並んでたらもっと楽なのでは」と思って配置を変えてみました。
結果、朝の支度がめちゃくちゃスムーズに!
歯ブラシ、洗顔、化粧水、整髪料を“使う順”に並べただけ。でもこれ、動線設計=UXそのものだったんですよね。
「動きやすい」「迷わない」「ストレスがない」。
こうした要素がすべて揃った状態をつくるって、まさにWebやアプリのUX設計と一緒です。
生活の中で、知らないうちに快適さのデザインをしていたんだなあと、ちょっと感動しました。
「整えること」は、学ぶ準備そのもの

ここからは、日常生活の中で整理整頓を徹底するとどのような変化が訪れるのかをお伝えしたいと思います。
- 独学で挫折した僕を救った整理整頓
- 思考の引き出しがあれば吸収も早い
- 普段の行動が学びを迎える土壌になる
独学で挫折した僕を救った整理整頓
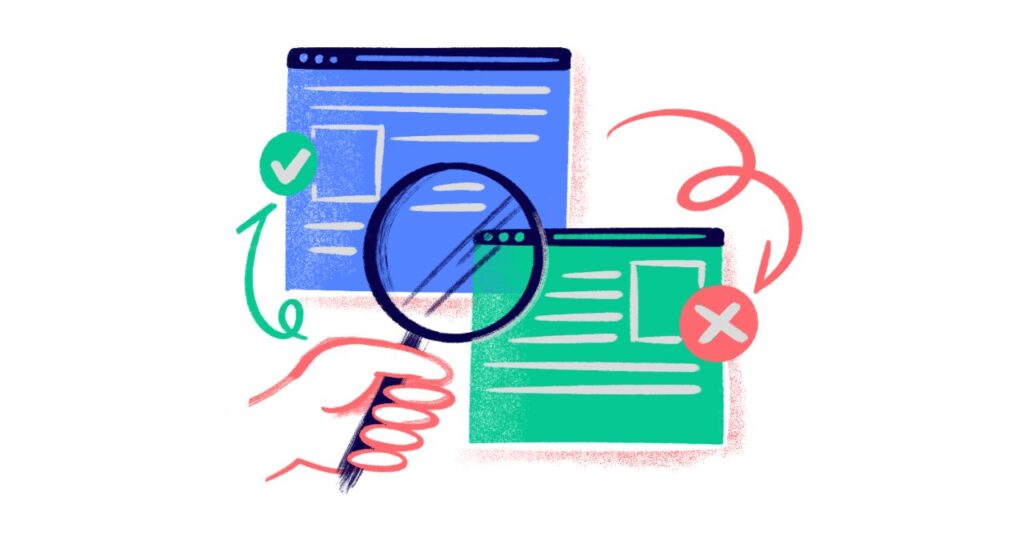
僕が最初にデザインを学び始めたのは独学でした。
デザイン書を読んで、YouTubeを見て、手探りで作品をつくって…とにかく情報に振り回されてました。
そのうち、フォルダが「素材」「素材(修正)」「素材(最終)」みたいになって、どれが何だか分からないカオスに(笑)
でもある日、「プロはまずフォルダを整える」って先輩に言われて、ハッとしました。思考の整理=アウトプットの精度なんだと。
それ以来、「まず整理から始めよう」が僕の学習スタイルの基本になりました。
思考の引き出しがあれば吸収も早い
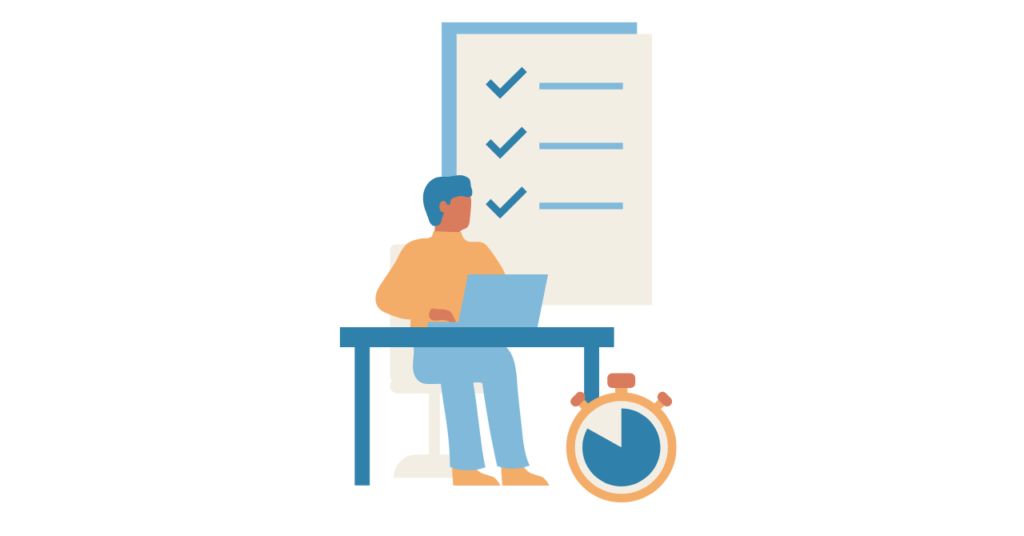
実際にスクールで学び始めたとき、整理癖がついているとカリキュラムの理解が物凄くスムーズになります。
「これは配色の話」「これは構成の話」「これはUXの話」と分類できるから、頭の中の引き出しが自然にできるんですよね。
情報が一気に頭に入ってこない人って、たいていこの「分類」ができていないだけだったりします。
だから、整理できる人は本当に強い。まさか掃除好きがここで役に立つとは思いませんでした(笑)
普段の行動が学びを迎える土壌になる

「私は絵が描けないから」「センスがないから」って、学ぶ前から不安になる人も多いけど、
実はそんなことより、「整える習慣」があるかどうかの方が、よっぽど大事だったりします。
家の中の動線、ノートのまとめ方、洗濯物の畳み方だっていい。
そういう生活の整え方が、学びを受け入れる“地ならし”になっているんです。
僕も、完全にそういうタイプでした。
だからこそ、「自分はまだ何もできない」と思わずに、「もう準備できてたんだ」って気づいてほしい。
今日からデザイン目線で暮らしてみよう

ここまで沢山のことを伝えてきました。
普段はあまり意識していなかったかも知れませんが、段々とデザインのことが分かると世界が少し変わって見えてきます。
- 意識するだけで世界の解像度が変わる
- 行動を変えれば、未来の自分が変わる
- 小さな一歩が、大きな変化を生む
今回学んだことを思い出しながら、また普段の生活を過ごしてみて下さい。
きっと昨日までは見えていなかった景色が見えるようになっていることでしょう。
意識するだけで世界の解像度が変わる
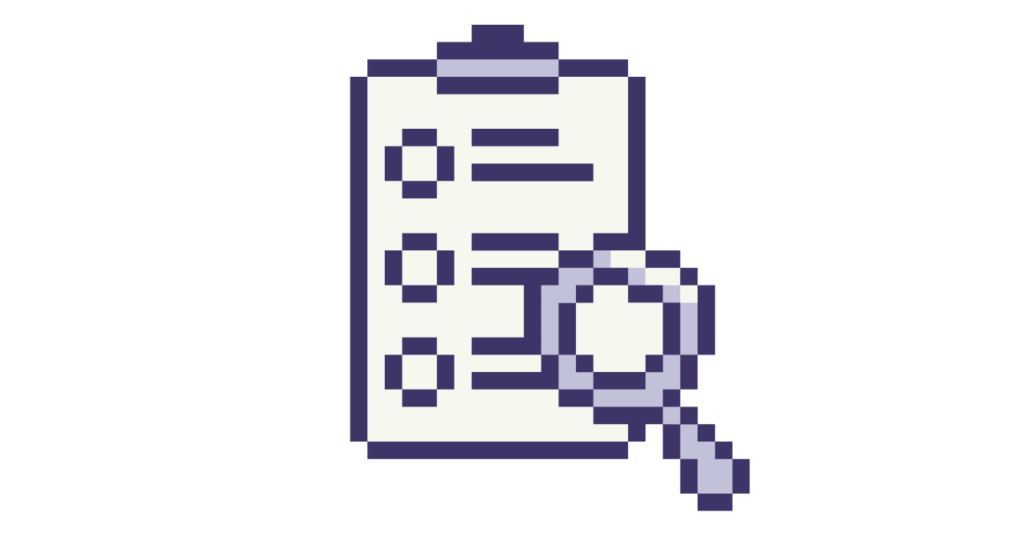
街を歩いていて、「あの看板、なんか読みやすいな」とか、コンビニで「この棚、なんでここにこの商品があるんだろう」とか──
そんなふうに、“ちょっと立ち止まって観察する”ことが、デザイン脳を育てる第一歩。
僕もデザインに興味を持ち始めた頃、ひたすら駅のポスターを観察してました。
文字の大きさ、視線誘導、色のバランス。普段なら素通りするような情報に気づき始めると、世界が少しずつ違って見えてくるんです。
これはまさに、“世界の見え方の解像度”が上がる瞬間。
デザインの学びって、何かを“作る力”じゃなくて、“気づく力”から始まるんですよね。
行動を変えれば、未来の自分が変わる
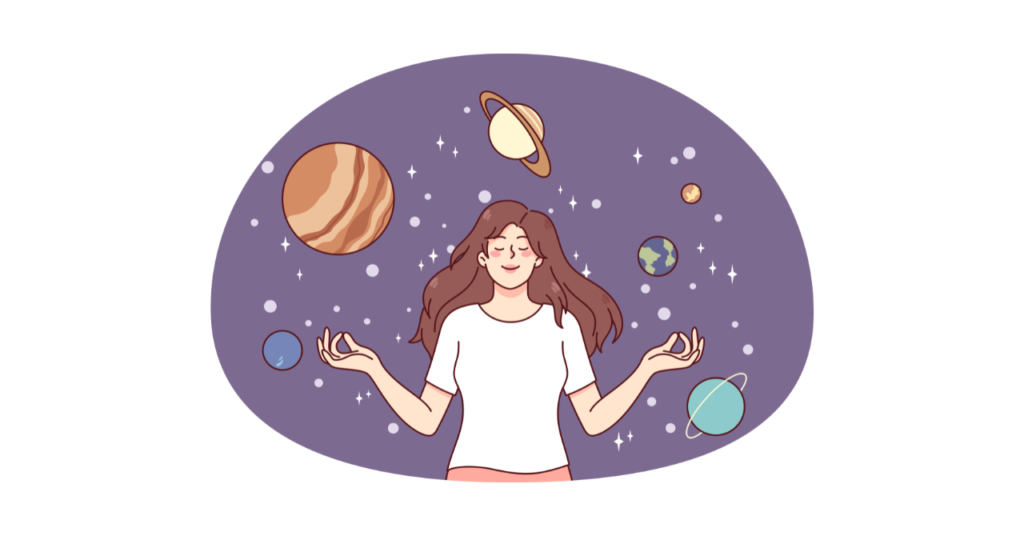
「自分には無理」「センスがない」と思っていた僕が、今こうしてデザインの本質を伝えるための文章を書いているなんて、当時は思いもしませんでした。
きっかけは、小さな行動の変化。
ToDoリストを見やすく整えてみたとか、ノートのまとめ方を工夫してみたとか、SNSの投稿を意識して構成したとか。
それだけで、「自分にもできるかも」って思える場面が増えてきたんです。
だからこそ、まずはちょっとだけ“目線”を変えてみてください。行動が変われば、自分への評価も、未来の選択肢も変わってきます。
小さな一歩が、大きな変化を生む

今日からできることは、ほんの些細なことかもしれません。
だけど、それを積み重ねてきた人が、いざ「学ぼう」と思ったときに、飛躍的に伸びるのです。
僕の知ってる限り、スクールに通って伸びた人って、事前に日常で“整える”習慣があった人ばかりでした。
だからあなたのその「生活の中での工夫」は、ちゃんと意味があるし、ちゃんと“伸びしろ”に変わります。
今日の選択が、半年後、一年後のあなたの可能性を広げるかもしれません。
本格的に学べる、おすすめのオンラインスクール

最後に。
ここまでの記事を読んでみて、本気でデザイン力を身に付けたいと思った人に僕がおすすめする厳選のスクールをお伝えします。
1つ目はデイトラ、2つ目はデジハリ・オンラインというデザインスクールです。
いずれのオンラインスクールも、デザイン業界で名前を知らない人は居ないという位有名なので安心して下さい。
デイトラは、自走力をつけたい人向け

デイトラは、とにかく「現場っぽい課題」で鍛えられるスクール。僕の知人も、未経験から数ヶ月で副業をスタートしてました。
- スマホでも学べる
- コミュニティで質問や交流も可能
- 実案件に近い課題で“仕事感覚”が身につく
短期間で、「自分で動ける力」をつけたい人にはぴったりのスクールです。
デイトラのことを初めて知ったという方は、別記事でデイトラについて詳しく執筆していますので、ぜひ参考にしてみて下さい。
\ 知名度もあって、コスパも抜群! /
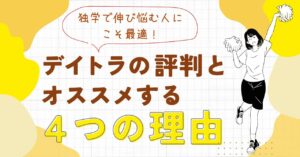
デジハリは、添削付きで学びたい人向け
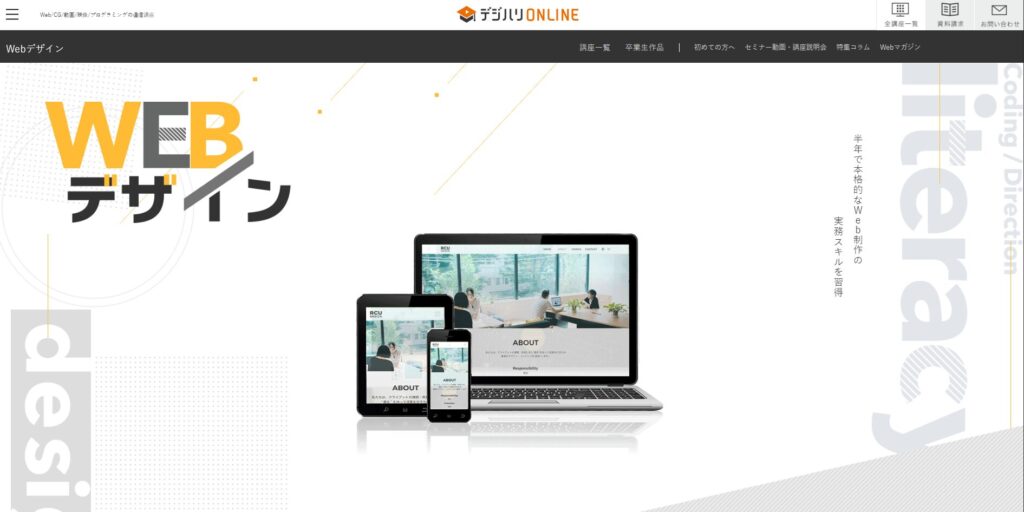
僕のように「これで合ってるのか?」と不安になりがちなタイプには、添削つきのデジハリが安心です。
デジハリは丁寧な指導で有名なので、初心者でも安心してデザインの勉強がスタートできます。
特に、「時間をかけてしっかり取り組みたい」人にはおすすめ。デジハリの簡単な特徴は以下の通り。
- プロ講師によるフィードバックで軌道修正ができる
- 学びの順序が整理されていて、迷いにくい
- Adobe CCは別途必要(セットではありません)
ちなみに。授業で使用するAdobeCCですが、既に契約している人は追加で料金を支払う必要はありません。
また、未契約の人でもデジハリの講座を通して申し込みをおこなえば割引価格で契約が可能です。
\ 手厚いサポートで、無理なく続けられる!/
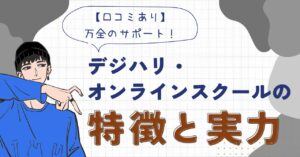
日常で育てた感覚を、スキルに変えよう

デイトラやデジハリ
に限らず、スクールは、「ゼロから何かを教えてもらう場所」ではなく「すでに自分の中にある感覚を、磨いて形にする場所」だと思っています。
「整えるのが好き」
「伝わりやすく工夫するのが得意」
そんな風に思えていたら、もう立派なデザインの芽が育っています。
そして、日常の中で育てた感性をスキルに変えてみたい人は、ぜひ自分に合ったスクールで専門的に学ぶことを検討してみて下さい。
デザインの力があれば、仕事やプライベートでも驚くほど世界が違って見えてきますし、だいぶ人生も生きやすくなると思います(笑)。
デイトラやデジハリ
以外の特徴のあるスクールについては、別記事にまとめてあります。これからスクールを選ぶ際の参考にしていただければと思います。
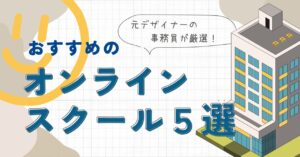
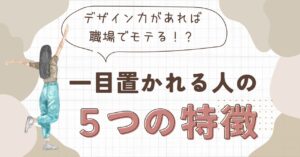
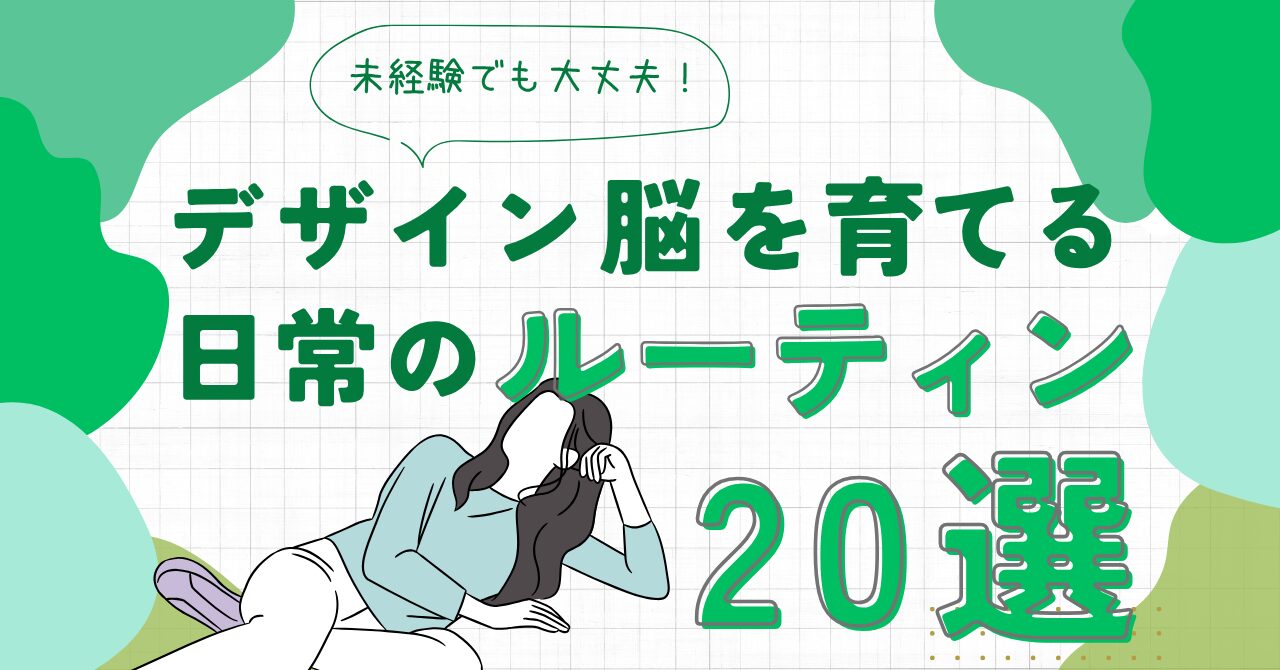
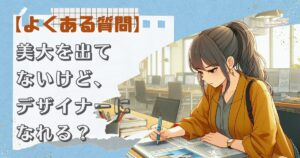

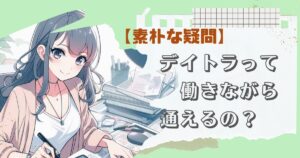

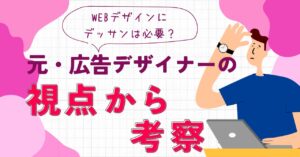
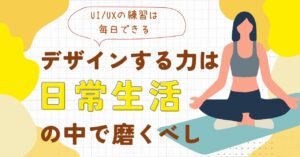
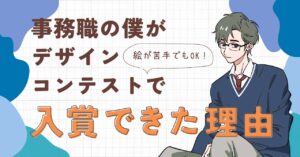
コメント