役所のチラシは「ちょっと古臭い」「読みづらい」と思われがちです。ですが、役所が発行するチラシは住民に必要な情報を届ける大切なツール。
ちょっとした工夫次第で、ぐっと見やすく、親しみやすく生まれ変わります。
今回は、役所チラシが陥りがちな3つの罠と、その回避法を具体的にお伝えします。
今回の記事が、あなたのチラシづくりのヒントになれば嬉しいです。
役所チラシにありがちな「見た目の残念さ」
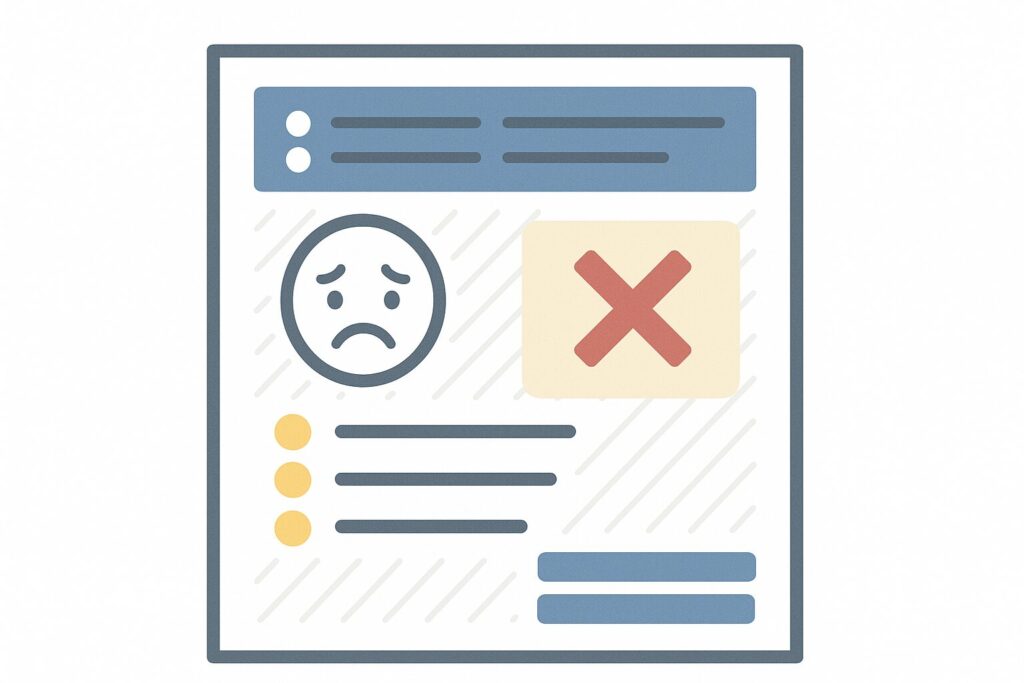
役所チラシや広報物を見たときに「なんだか古臭いな…」「ごちゃごちゃして読みにくいな」と感じることはありませんか?
それは、実は単なる印象ではなく、チラシの作り方やデザインに原因があります。
役所チラシは、正確な情報を盛り込むことが最優先になりがち。結果として、デザイン性が後回しになってしまうことが多いのです。
以下は、よく見かける「見た目の残念さ」のパターンです。一度あなたの職場のチラシを思い浮かべて、チェックしてみてください。
- 地味な色合いばかりで目立たない
- 情報が多すぎて読む気が失せる
- 文字ばかりで、イメージが湧かない
もし1つでも当てはまったら、それは改善の余地があるサインです!
役所チラシがダサく見える“3つの罠”

役所チラシの「ダサ見え」には、よくあるパターンが存在します。
ここでは、特にありがちな3つの罠を紹介します。あなたのチラシにも思い当たる部分がないか、ぜひ照らし合わせてみてください。
- 配色の罠
- フォント選びの罠
- 情報の詰め込みすぎの罠
では、それぞれの罠について詳しく見ていきましょう。
1. 配色の罠
配色はチラシの印象を決める大切な要素です。役所チラシでは、控えめな色合いばかりを使ってしまい、全体が地味な印象になることが多いです。
逆に、色を多用しすぎてしまい、バラバラで統一感がなくなる例もあります。
配色のバランスが崩れると、住民の目に留まりにくく、せっかくの情報が届かなくなってしまいます。
2. フォント選びの罠
フォントの選び方は、読みやすさや印象を大きく左右します。
役所チラシでは「明朝体やゴシック体だけで統一」といった無難な選択が多く、見出しと本文の区別がつかないことも。
読み手にとっては「どこから読めばいいのかわからない」というストレスにつながります。
3. 情報の詰め込みすぎの罠
「伝えたいことが多いから」と、必要以上に文字を詰め込んでしまうことはありませんか?
役所のチラシは住民に役立つ情報を伝える使命があるからこそ、つい情報を盛り込みすぎてしまいがち。
ですが、結果として読み手が「読む気をなくすチラシ」になってしまうのは本末転倒です。
情報を取捨選択する視点も欠かせません。
どうすれば回避できる? デザインの基本3ポイント

「ダサく見える3つの罠」を回避するためには、デザインの基本を押さえることが重要です。
ここでは、役所チラシでもすぐに試せる3つの基本ポイントを紹介します。
- 色のルールを決める
- フォントにアクセントをつける
- 余白を活かす意識を持つ
この3つのポイントを知っているだけで、役所チラシの印象は驚くほど変わります。
1. 色のルールを決める
「色数が多いとカラフルでいい」…これは間違いです。
配色の基本としてオススメなのが「7:2:1ルール」。
ベースカラーを7割、アクセントカラーを2割、補助カラーを1割に抑えると、統一感が出て落ち着きのある印象になります。
役所チラシでも、このルールを意識するだけで洗練された印象をつくれます。

2. フォントにアクセントをつける
見出しと本文を同じフォントにすると、情報が埋もれてしまいます。
見出しにはインパクトのあるフォントを使い、本文は可読性を意識したものにする。
さらに補足情報や注釈は別のフォントにするなど、役割分担を意識すると視線の流れが自然に生まれます。

3. 余白を活かす意識を持つ
情報を詰め込みすぎると、チラシはすぐに「文字の壁」になってしまいます。
空白=無駄なスペースではなく、情報を引き立てる“間”です。
余白をしっかりと確保するだけで、読み手が呼吸をするように情報を吸収できます。
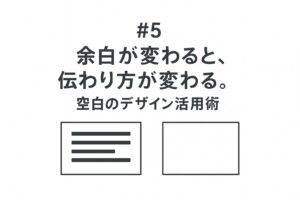
役所チラシをもっと“伝わるデザイン”にするには?

「3つの基本」で整えたら、もう一歩踏み込んで“伝わるデザイン”を目指しましょう。小さな工夫でも、大きな印象アップにつながります。
以下の4つの視点を意識してみてください。
- 「誰に伝えるか」を明確にする
- 情報の優先順位を決める
- イラストやアイコンを活かす
- 住民目線の「親しみやすさ」を意識する
この4つを押さえれば、役所チラシの印象はぐっと良くなります!
1. 「誰に伝えるか」を明確にする
住民向けなのか、観光客向けなのか。相手が変われば必要な情報も変わります。
まずは「誰に向けて届けるのか」をはっきりさせることで、チラシの目的が明確になります。
2. 情報の優先順位を決める
すべての情報を同じ大きさで載せるのは逆効果。
重要な見出しやキャッチコピーは大きく、目を引く位置に置く。補足情報は、読みたい人が自然と読めるように配置する。
視線誘導を意識することで、見やすさがぐっと向上します。
3. イラストやアイコンを活かす
文字だけだと固い印象になりがち。イラストやアイコンは、内容の理解を助けるだけでなく、親しみやすさを生みます。
役所チラシでも、ちょっとした挿絵やピクトグラムを入れるだけで、全体がやわらかくなります。
4. 住民目線の「親しみやすさ」を意識する
役所らしい真面目さを残しながら、色やフォントを少し柔らかく調整するのも効果的です。
住民にとって「見やすい」「読んでみよう」と思えるデザインは、親しみやすさが決め手になります。
役所チラシも“デザインの工夫”で変わる!
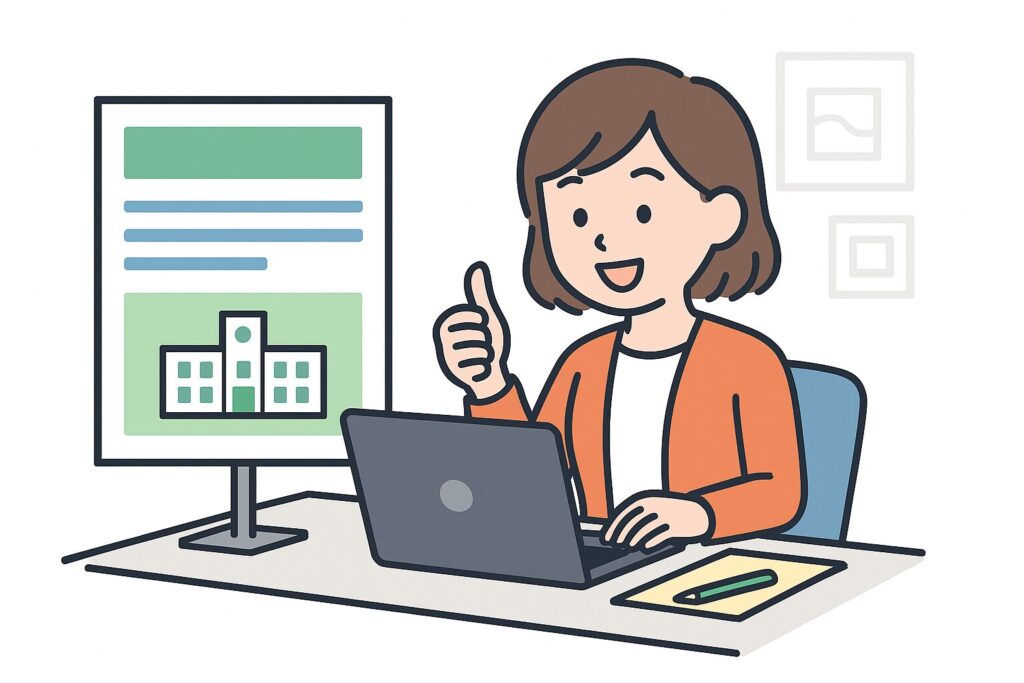
役所チラシは、ほんの少しの工夫でぐっと印象が変わります。
情報はもちろん大切ですが、同じ情報でも「伝わりやすさ」はデザイン次第です。
今回紹介した3つの罠とその回避法、さらに4つの視点を意識するだけで、きっとあなたのチラシも見違えるはずです。
住民にとって、役所からの情報は生活に欠かせないもの。
だからこそ、読みやすく、親しみやすいチラシを目指してみませんか?
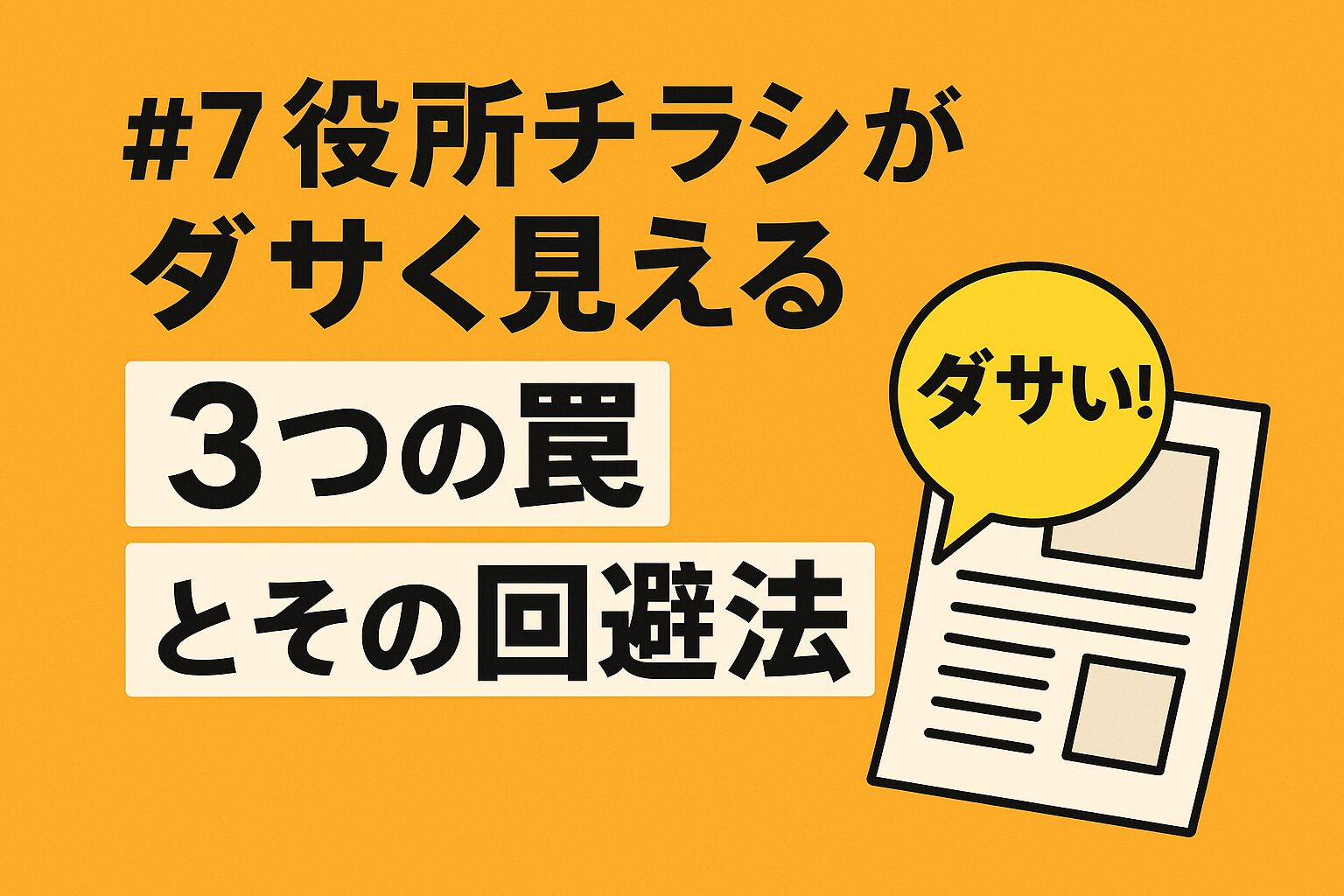

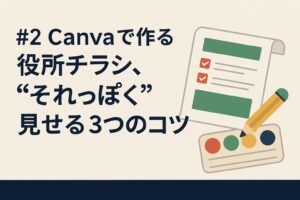



コメント