 悩む人
悩む人Webデザインに興味があるけど専門学校とオンラインスクール、どっちに通うのがいいのかな?
確かに、どちらも同じような内容が学べますよね。カリキュラムにも一長一短あるので、一概には言えませんが…
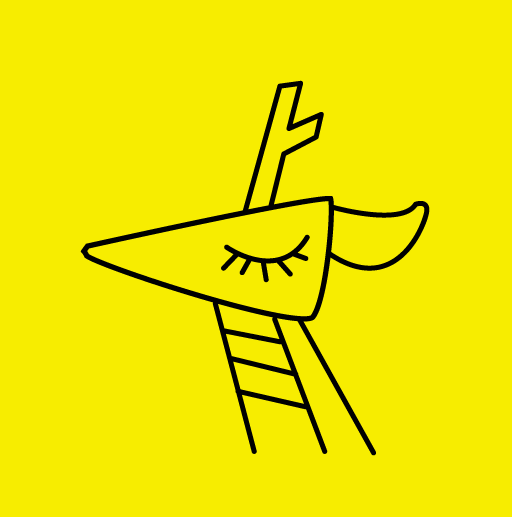 ぴりおど
ぴりおどただ、社会人ならオンラインスクールの方を断然おすすめします!
かつて僕が専門学校に通っていた当時は、まだオンライン授業なんてほとんど聞いたことがありませんでした。
教室に通って、先生の話をノートに取りながら聞くのが当たり前の時代。
デザインは「現場で手を動かして覚えるもの」だと思い込んでいて、それが最短ルートだと信じて疑いませんでした。
もちろんオンラインでの授業と違って、教室受講には教室受講の良さがあります。
でも、あれから時代は大きく変わりました。
今の僕は、かつてのこだわりを捨ててデイトラというオンラインスクールでWebデザイン講座を再び学び直し中。
空いた時間に自宅で動画を見ながら課題を進めるという、昔の自分なら信じられないような学習スタイルでWebデザインのことを学んでいます。
今回の記事では専門学校とスクールの違いについて、自分の体験を交えながら本音で語ってみたいと思います。
「専門学校とスクールだったら、どっちに通うのが正解なんだろう?」と迷っている人のヒントになれば幸いです。
専門学校とスクールの違いって何?

一口に「デザインを学ぶ」といっても、選択肢はいろいろあります。代表的なのが「専門学校」と「スクール(オンライン含む)」の2つ。
両者はよく似ているように見えて、目的・時間・お金・自由度など、実はかなり違います。ここでは、その基本的な違いを整理しておきます。
学べる内容の深さと広さ
専門学校は2〜3年かけて、デザインの基礎から応用、印刷・写真・映像・企画…と幅広く学べます。
僕も当時、IllustratorやPhotoshopの使い方だけでなく、構成や色彩、デザイン史など「座学」もしっかりやりました。
一方、スクール(特にオンライン)は、必要なスキルにぐっと焦点を当てて、短期間で実践的に学べるのが特徴です。
たとえば、僕が今学んでいるデイトラは、「Webデザインに必要なスキルだけ」を効率よく学べる構成になっています。
\ 知名度もあって、コスパも抜群! /
学習期間と自由度
専門学校は基本的に平日通学が前提。
授業時間も固定で、アルバイトや他の予定と両立するのはなかなか大変でした。
毎日、1時間半かけて通学していましたが、今思えば良くやっていたなあと思います。
一方、スクールはその逆。特にオンラインスクールは、パソコンやスマホがあれば「いつでも・どこでも」学べるのが大きな魅力。
僕も仕事の合間や夜の空いた時間に、マイペースに学習を進めています。
週末などの大きく時間が空いた時には、一気に講義や課題を進められるのでスケジュールがとても調整しやすくなりました。
費用の違い
専門学校とスクールで最も違いが出るのが、やはり授業料や施設管理費などの費用面でしょう。
専門学校だと通常、年間100万円以上授業料が掛かるのが一般的で、2年通えば200万円超えも珍しくありません。
奨学金や教育ローンを組む人も多いですし、実際に僕が通っていた当時も何人かのクラスメートがそういった支援を受けていました。
さらに、通学するために必要な定期券などの交通費、毎日のご飯代や飲み物代もバカになりません。
一方のオンラインスクールは、授業料という点ではかなりリーズナブル。
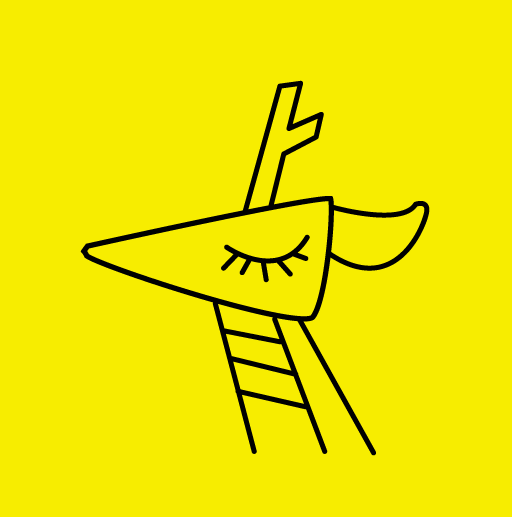 ぴりおど
ぴりおどたとえば、僕が受講したデイトラの「Webデザイン講座」は買い切り型で約13万円ほどです。
しかも、デイトラの場合は一度講義を聴いたら終わりではなく、アップデートされる教材を卒業後も永続的にオンラインで閲覧できます。
専門学校は卒業したら普通はそれでおしまいですので、その差は正直かなり大きいです。
オンラインスクールなら基本は自宅で受講できるので交通費は掛かりませんし、食事も家にあるもので安く済ませることができます。
台風や雪の日でも問題なく授業が受けられますし、ストレスのかかる満員電車に揺られながら通学する必要もありません。
\ 知名度もあって、コスパも抜群! /
僕がデザイン専門学校に通って感じたこと

じゃあ専門学校がダメだったかというと、決してそうではありません。
ここからは、僕が専門学校に通ってよかったこと、そして気づいたことについて話していきます。
専門学校に通って良かったこと3選
専門学校に通って良かったと思うことは、以下の3点です。
- 基礎力がしっかり身についた
- 先生や仲間とリアルな交流ができた
- 生活のすべてが“デザイン漬け”になった
基礎力がしっかり身についた
専門学校では、デッサン・色彩構成・レイアウト・タイポグラフィなど、基礎的な技術を繰り返し叩き込まれました。
課題のたびに「なぜこの配置にしたの?」「この配色の意図は?」と問われ、自分なりに言語化して提出することで、思考力も鍛えられたと思います。
今でも「このときに身につけた“土台”があるからこそ、応用が効くんだな」と実感する場面が多いです。
先生や仲間とリアルな交流ができた
授業の合間に先生に雑談交じりで質問したり、友人の作品を見て刺激を受けたりと、対面ならではのやりとりは本当に大きな財産です。
同じように悩んでいる仲間と「こんなやり方もあるんだ」「なるほど、そういう見せ方もあるんだ」と、自然と視野が広がっていきました。
個展や卒展の準備も含めて、協力し合いながら成長できる環境だったと思います。
生活のすべてが“デザイン漬け”になった
通学・制作・発表・展示と、すべてが「デザイン中心」の生活でした。
移動中もポスターを観察したり、雑誌を切り抜いてアイデア帳に貼ったりと、毎日がトレーニングのような感覚。
「やるなら今しかない」と全力で没頭できたことは、学生時代ならではの贅沢だったと思います。
専門学校に通って悪かったこと3選
専門学校に通って悪かったと思うことは、以下の3点です。
- 時間の拘束が多く自由が少なかった
- 費用がかなり高かった
- 卒業後の進路が見えづらかった
時間の拘束が多く自由が少なかった
朝から夕方までみっちり授業が詰まっており、そのあと課題や作品制作に取りかかるとなると、1日があっという間に終わります。
プライベートや自分の趣味の時間を確保するのが難しく、当時は正直、心身ともにけっこうギリギリな生活をしていました。
費用がかなり高かった
授業料・施設費・PCやソフト代・印刷代・画材費…と、気づけば出費がどんどん増えていました。
通学にかかる交通費や、毎日の昼食代も合わせると「本当に元が取れるのかな…」と何度も思った記憶があります。
今のオンラインスクールの料金を見ると、やっぱり“高すぎたな”と感じざるを得ません。
卒業後の進路が見えづらかった
卒業=即プロ、ではありませんでした。ポートフォリオ制作やインターン探しは自力で動く必要があり、情報収集も手探り状態。
進路に迷っていた僕にとっては、学費の元を取る前に「不安」が先に来てしまったのが正直なところです。
僕がデザインスクールに通って感じたこと

デザインの世界から一度離れて、事務系の仕事に就いたあとも、
「また、ものづくりをしたい」
「何かを表現する力を取り戻したい」
そんな気持ちは、ずっと心のどこかに残っていました。
でも、大人になってからもう一度、専門学校に通い直すのは正直ハードルが高い。お金も時間も限られているし、通学の時間を毎週確保するのも難しい。
「それでも、もう一度デザインを学びたい」
そんなときに出会ったのが、オンラインスクールという新しい選択肢でした。
オンライン講座で良かったこと3選
オンライン講座を受講して良かったと思うことは、以下の3点です。
- 必要なスキルに絞って効率的に学べた
- 時間も場所も自由に学べた
- コスパが圧倒的に良かった
必要なスキルに絞って効率的に学べた
専門学校のように広く浅く学ぶのではなく、自分の目的に直結した内容だけを選んで学べるのが大きなメリット。
たとえば、僕が受講したデイトラでは「Webデザイン」に必要なスキルだけがぎゅっと詰まっていて、遠回りせずに学べる構成になっていました。
「まずはここまでできるようになろう」というステップも明確で、社会人でも学びやすいと感じました。
\ 知名度もあって、コスパも抜群! /
時間も場所も自由に学べた
通勤前の早朝30分、昼休みのスキマ時間、夜の1時間…というように、自分のペースで進められるのが本当に助かりました。
「今日は疲れたから休もう」「週末にまとめて進めよう」など、生活リズムに合わせて無理なく学習できるのは、社会人にとって大きな魅力です。
コスパが圧倒的に良かった
デイトラだと13万円ほどの買い切りで、しかもアップデートされた教材をずっと見られる仕組みには驚きました。
専門学校のような高額投資をしなくても、ここまで学べるのか…と、最初は半信半疑でしたが、教材の内容もしっかりしていて納得。
金額的なハードルが低いからこそ、「まず始めてみる」がしやすいと感じました。
オンライン講座で悪かったこと3選
オンライン講座を受講して悪かったと思うことは、以下の3点です。
- 孤独を感じやすい
- 自己管理が必要
- 対面のサポートが少ない
孤独を感じやすい
誰かと一緒に進めるわけではないので、モチベーションを保つのが難しい日もあります。
質問もチャットベースなので、すぐに返答がもらえないときは不安になりますし、「このやり方で合ってるのかな…?」と自信を持ちづらいことも。
自己管理が必要
提出〆切があるわけではないので、学習をサボろうと思えばいくらでもサボれます。
僕も最初の1週間はハイペースだったのに、気を抜いたら何日間かマルっと手をつけていない時期もありました。
意志の強さと、目標設定のスキルがけっこう大事になります。
対面のサポートが少ない
講師の添削やチャットの回答はありますが、実際に横で「ここをこう直してみよう」と手取り足取り教えてくれるわけではないので、ややもどかしいです。
「言葉では分かるけど、実際にどう直せばいいの?」と迷う場面では、専門学校の対面授業がちょっぴり恋しくなることもありました。
\ 知名度もあって、コスパも抜群! /
専門学校派?スクール派?【目的別診断】

ここまで読んで、「結局、どっちがいいの?」と思っている人もいるかもしれません。
実際は、どちらかが正解というよりも、目的や状況によって向き不向きが分かれると思います。
以下に、ざっくりとした目安をまとめてみました。
専門学校が向いている人の特徴
僕が専門学校に向いていると思う人の特徴は、以下の通り。
- 10代〜20代前半で、時間がたっぷりある
- いろんなジャンルのデザインを広く学びたい
- 同世代の仲間と切磋琢磨したい
- 学割や就職サポートをフル活用したい
スクールが向いている人の特徴
僕がスクールに向いていると思う人の特徴は、以下の通り。
- 社会人や主婦など、限られた時間の中で学びたい
- 必要なスキルだけを、効率的に身につけたい
- すぐに副業や在宅ワークに活かしたい
- 通学に時間もお金もかけたくない
僕自身が「もう一度デザインを学びたい」と思ったとき、専門学校ではなくスクールを選んだのは、まさにこの「今の自分に合っている」という視点があったからです。
専門学校やスクールの資料、無料動画を見てみよう

専門学校とスクール、それぞれにそれぞれの良さがあります。ただ、いきなり申し込むのはハードルが高いし、僕も最初は慎重でした。
でも今は、多くの専門学校やスクールが「無料体験」や「カリキュラム紹介動画」を用意してくれています。
雰囲気だけでも見ておけば、「思ってたのと違った…」というミスマッチも防げます。
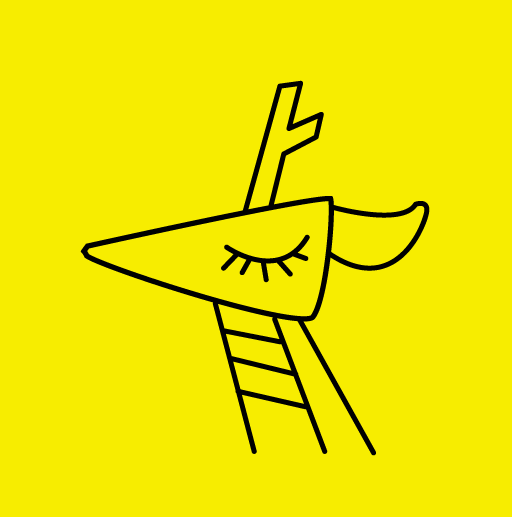 ぴりおど
ぴりおど僕にとっては、専門学校は「基礎力」を、スクールは「再スタートのきっかけ」をくれました!
たとえば、僕が受講中のオンラインスクールのデイトラでは、以下のような内容を無料でチェックできます。
- 各章の内容を細かく確認できるカリキュラムの公開
- 学習者のリアルな声や成果物の紹介
- 講座のアップデート情報や学習サポート体制
いずれも公式ホームページから見れるので、他のスクールや専門学校と検討している人はぜひチェックしてみてください。
今の時代、学び直しは遅くない。むしろ、自分のタイミングで始められるチャンスがある時代です。
まずは一歩、気軽に学校案内の資料、無料動画からのぞいてみてくださいね。
\ 知名度もあって、コスパも抜群! /
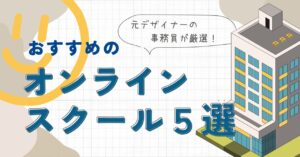
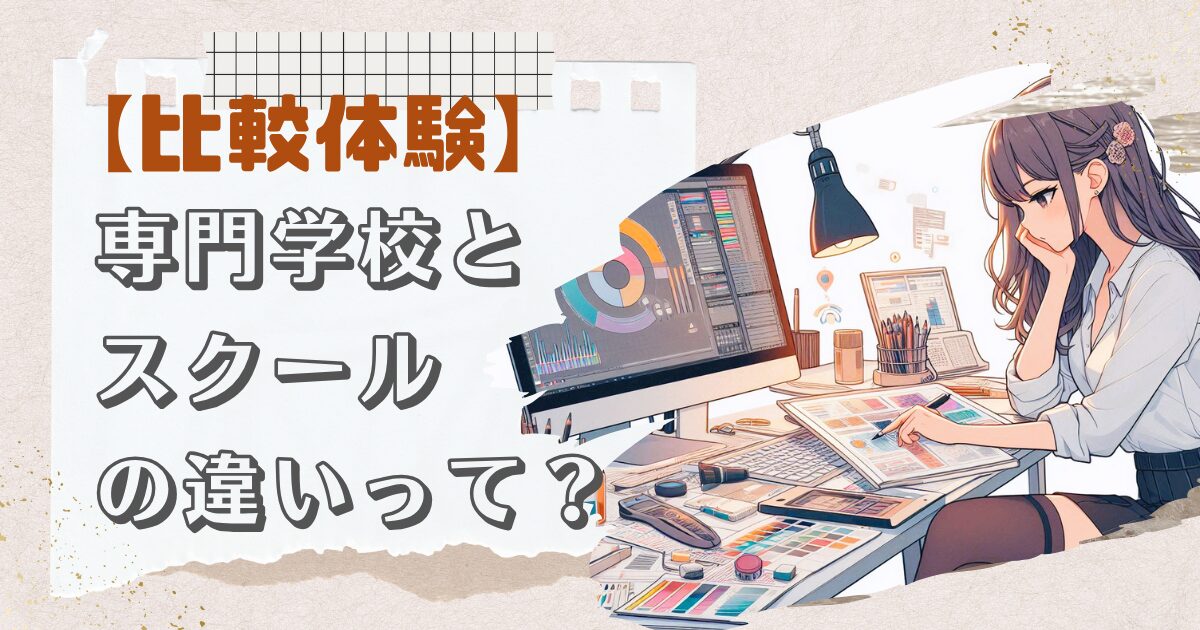
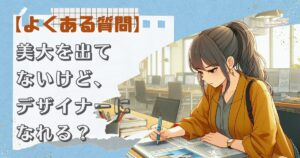

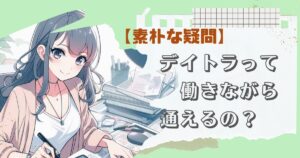

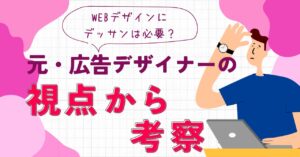
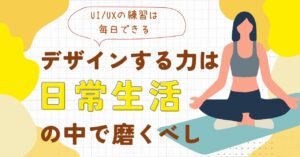
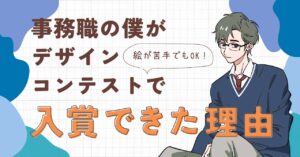
コメント